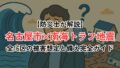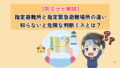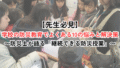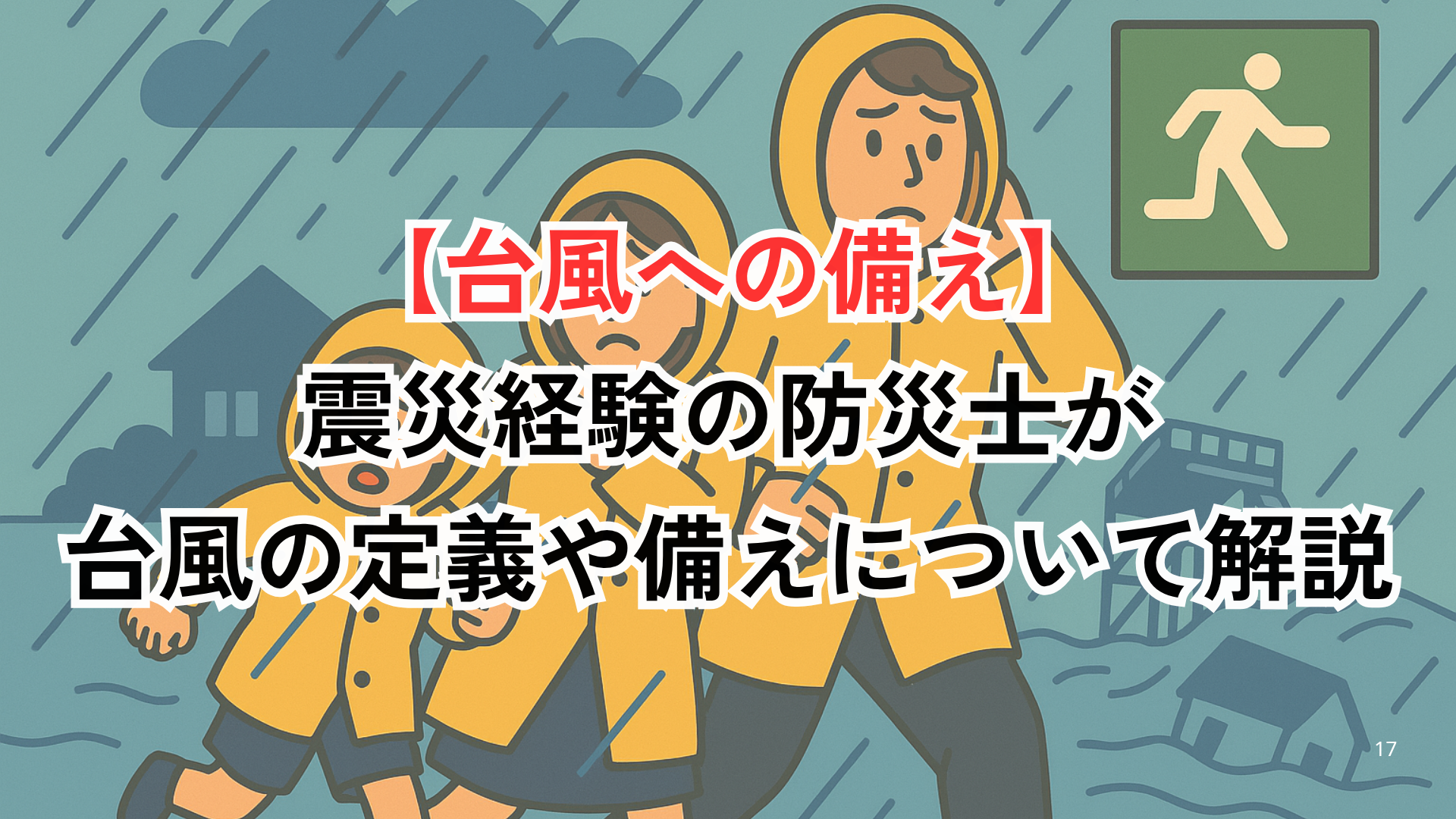こんにちは!
9年前の今日である2016年4月14日は熊本震災が発生した日です。
当時私は今働いている会社に入社したばかりで同期達と過ごしていました。熊本出身の同期もいるため「実家は大丈夫だったか?」などの話をずっとしていました。
そんな私ですが中学1年生の時に東日本大震災を経験しました。海からすぐの学校から津波と鬼ごっこをして小・中学校と地域住民含めて600人弱が助かることが出来た「釜石の奇跡」の当事者となります。
そして語り部として当時の経験談を語る啓蒙活動を行っております!
詳しくはこちらの記事から!
突然ですが、みなさんは「災害=地震の揺れで家が倒れること」と思っていませんか?
たしかにそれも大きな被害ですが、実は命に関わるのはそれだけではないんです。
2016年4月、熊本県で起きた「熊本地震」。
この地震では、多くの方が建物の倒壊や揺れで被害を受けましたが――
それ以上に深刻だったのが、避難生活の中で命を落とす「災害関連死」の多さでした。
この記事では、熊本地震の具体的な被害、そしてそこから見えてきた“これからの防災のあり方”について、わかりやすくお話ししていきます。
■ 熊本地震ってどんな地震だったの?
まず簡単に、熊本地震の概要をおさらいします。
- 発生:2016年4月14日(前震)・16日(本震)
- マグニチュード:M6.5(前震)→M7.3(本震)
- 最大震度:震度7(2度観測)
- 被害:死者273人(うち223人が災害関連死)、負傷者2800人以上、住宅の被害は約20万棟以上
「震度7が2回」って、とんでもないですよね。
実はこの地震、最初に来たのが前震で、2日後にさらに大きな本震が来たため、被害がより大きくなりました。
しかも、この地震の特徴は“浅い直下型”だったこと。
つまり、震源がすごく地表に近かったので、ドカン!と激しく揺れたわけです。
● 地域ごとの被害状況
◎ 熊本市 熊本市では、特に中央区・東区などで震度6強~7の強い揺れがあり、古い木造住宅の倒壊が相次ぎました。マンションでも内壁の亀裂やエレベーターの停止、断水・停電などインフラ被害が広がりました。
◎ 益城町(ましきまち) 最大震度7を2度記録した、最も被害が大きかった地域です。住宅の約8割が全壊または半壊し、町の中心部は一面の瓦礫と化しました。避難所も早々に満員になり、車中泊を余儀なくされた住民も多く、関連死も目立ちました。
◎ 南阿蘇村 阿蘇地方では大規模な土砂崩れが発生し、特に南阿蘇村立野地区では、阿蘇大橋が土砂災害とともに崩落。学生が乗っていた乗用車も巻き込まれるという痛ましい事故もありました。また、土砂で孤立した集落が多数発生し、支援が届くまでに時間がかかりました。
◎ 西原村・御船町 山間部では地滑りや斜面崩壊が相次ぎました。道路の寸断や断水、土砂で埋まった家屋などが相次ぎ、復旧まで長い時間がかかった地域でもあります。
◎ 八代市・宇城市 比較的揺れの規模は小さかったものの、液状化や漁港の護岸被害が報告されました。沿岸部では地盤が弱く、インフラの再整備に時間がかかりました。
◎ 火災の発生 地震の揺れによる火災も複数件確認されています。特に益城町では住宅火災が発生し、消防の出動も難航しました。ガス管の破裂や漏電などが原因とされており、揺れに加えて火災による二次被害も深刻でした。
こうして見ると、熊本地震は単に「強く揺れた」というだけでなく、地形や建物の状況、地域の条件によって様々な被害をもたらしたことがわかります。
他にも家の区画としてブロック塀を建てている住宅などは経年劣化により熊本地震で決壊してしまった事例がかなり多くありました。
本当に怖かったのは、「避難生活」だった
さて、熊本地震で命を落とした方のうち、実際に地震の揺れで亡くなった人は50人。
それに対して、避難所での生活や体調悪化によって亡くなった人は223人にものぼります。
震災による建物倒壊や火災などの直接よりも避難所生活以降の災害関連死で亡くなった人が多いのです。これが、熊本地震が私たちに残してくれた一番大きな教訓かもしれません。
たとえば…
- 体育館で雑魚寝→血栓ができて「エコノミークラス症候群」に
- 持病の薬が足りない、医者に行けない→病状悪化
- トイレが遠くて我慢→脱水症状や感染症
- 精神的ストレス→うつ状態になり、食事が喉を通らなくなる
こうした「避難生活のストレスや体調悪化」によって、命を落とす人が後を絶ちませんでした。
熊本地震の避難所、何が起きていた?
熊本では一時、18万人以上の人が避難所で暮らしていました。
でも、どの避難所も同じように支援されていたかというと、そうではありません。
避難所が「超過密」
多くの人が押し寄せた避難所では、1人あたりのスペースがわずか1畳なんてことも。
プライバシーはゼロ。トイレも行列。感染症も怖い…。
車中泊の危険
「避難所が混んでいるから車で寝よう」と選んだ人が多かったのですが、これがまた危険。
狭い車内で長時間同じ姿勢でいると、足に血栓ができて命を落とす「エコノミークラス症候群」になる恐れがあります。
車が無い方は過密された避難所で身動きを取れず動かず過ごしている方もエコノミークラス症候群になります。
実際、熊本でも車中泊で亡くなった方が多数報告されました。
情報が届かない
どこの避難所に物資があるのか、誰がどこにいるのか、わからない。
結果、支援が偏ったり、孤立した避難所が出てしまったり…。
これからの防災は「避難所運営」がカギ!
さて、ここまで読んできてわかる通り、
今の日本で災害から命を守るには、「建物の耐震」だけじゃ足りません。
避難所の環境をどう整えるか。
誰が運営して、どんな支援を受けられるのか。
それを事前に考えておくことが、命を守るカギなんです。
私達が備えるべき防災アクションは?
ここからは、熊本地震の教訓をふまえて、私たちが普段からできる備えを紹介します。
1. 非常持ち出し袋に“生活の質”を守るものを!
水・食料だけじゃなく、以下のようなものもぜひ入れておきましょう!
- アイマスク・耳栓(避難所での安眠)
- ウェットティッシュ・除菌グッズ
- 生理用品・おむつ・簡易トイレ
- 常備薬・お薬手帳のコピー
- 歯ブラシ
- ボディークリーム(ニベア缶など)
2. 自分の町の“福祉避難所”を確認しておこう
高齢者や障がい者、乳児を連れた家庭などは、一般の避難所よりも配慮された**「福祉避難所」**の利用が必要です。
でも、意外と場所を知らなかったりしますよね?
お住まいの自治体のホームページなどで事前に確認しておくのがおすすめ!
3. 地域の避難訓練に参加してみる
「参加するのちょっと面倒くさいな~」って思うかもですが…
実際にやってみると、「え、こんなところが避難所なの?」とか「誰が仕切るの?」とか、気づきがいっぱいあります。
いざというとき、自分や家族の命を守れるかどうか、そこで差が出るんです。
4. ハザードマップを確認する
避難場所を調べて、避難訓練をすることも大事です!
ただ実際に自分が普段いる職場や家は災害のリスクはないのか?こちらも調べる必要があります!
調べ方が分からない方は私がオススメするハザードマップポータルサイトを推奨します!
使用方法は以下の記事を見てください!
5. 在宅避難が可能であれば家に備蓄しよう
ハザードマップを見て明らかに自分の家は災害のリスクが低くて災害後に家に避難できそう!
という状況であれば在宅避難をオススメします。それは熊本地震の避難所生活で分かる通り、災害関連死に繋がる生活をする可能性が高いからです。
最初に避難場所へ避難して、落ち着いてから家に避難できる方はできるだけストレスがかからない家に避難して下さい。
そして家の中で非常食や非常用トイレなどを備蓄して、電気や水が復旧するまで生活をしましょう!
■ 熊本の経験を、次の災害に活かそう
熊本地震は、多くの命が失われたつらい災害でした。
でも、その分、多くの「教訓」や「改善のきっかけ」も残してくれました。
- 災害関連死を減らすには、避難所の環境が大事
- 要支援者や車中泊者など、“見えない被災者”への支援も必要
- 情報の共有と地域の助け合いが命を守る
この学びを、南海トラフ地震や首都直下地震など、これから予測される大災害に活かさない手はありません。
最後に:防災は「自分ごと」にしてこそ
防災って、正直ちょっと難しく感じたり、「どうせ他人事でしょ」って思ったりしがちですよね。
でも、地震はいつ・どこで起きるか分かりません。
被災者のリアルな声は、「まさか自分が」の連続でした。
熊本の方々が、命と引き換えに残してくれた教訓を、今このタイミングで私たちが学び、行動に移せば、
未来の“誰かの命”が、もしかしたら“あなたの大切な人の命”が守れるかもしれません。
今日できる小さな一歩、ぜひ踏み出してみてくださいね。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
気になることや「こんな備え、役立ったよ!」などあれば、ぜひコメントで教えてください!