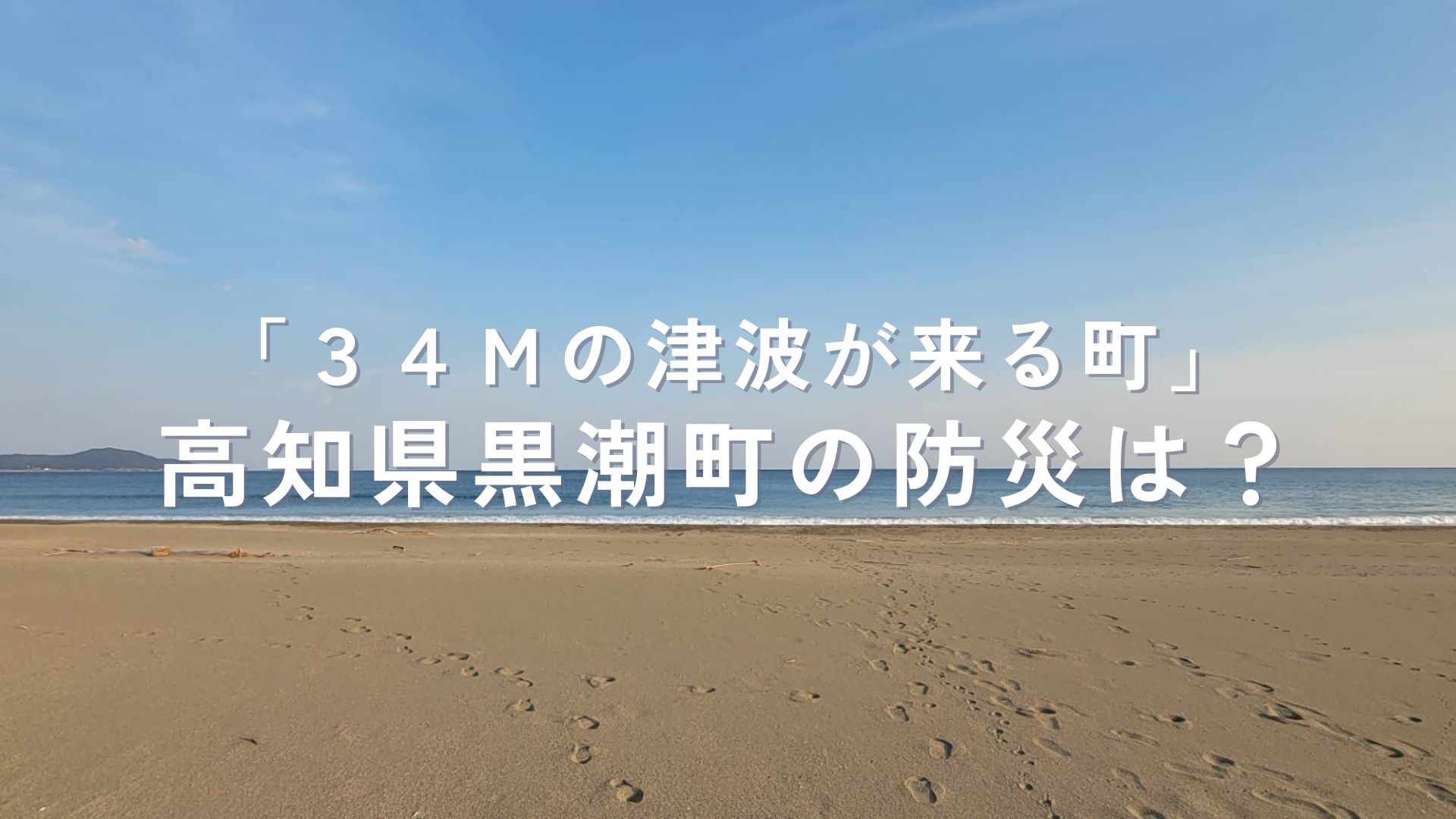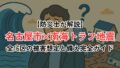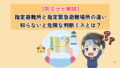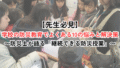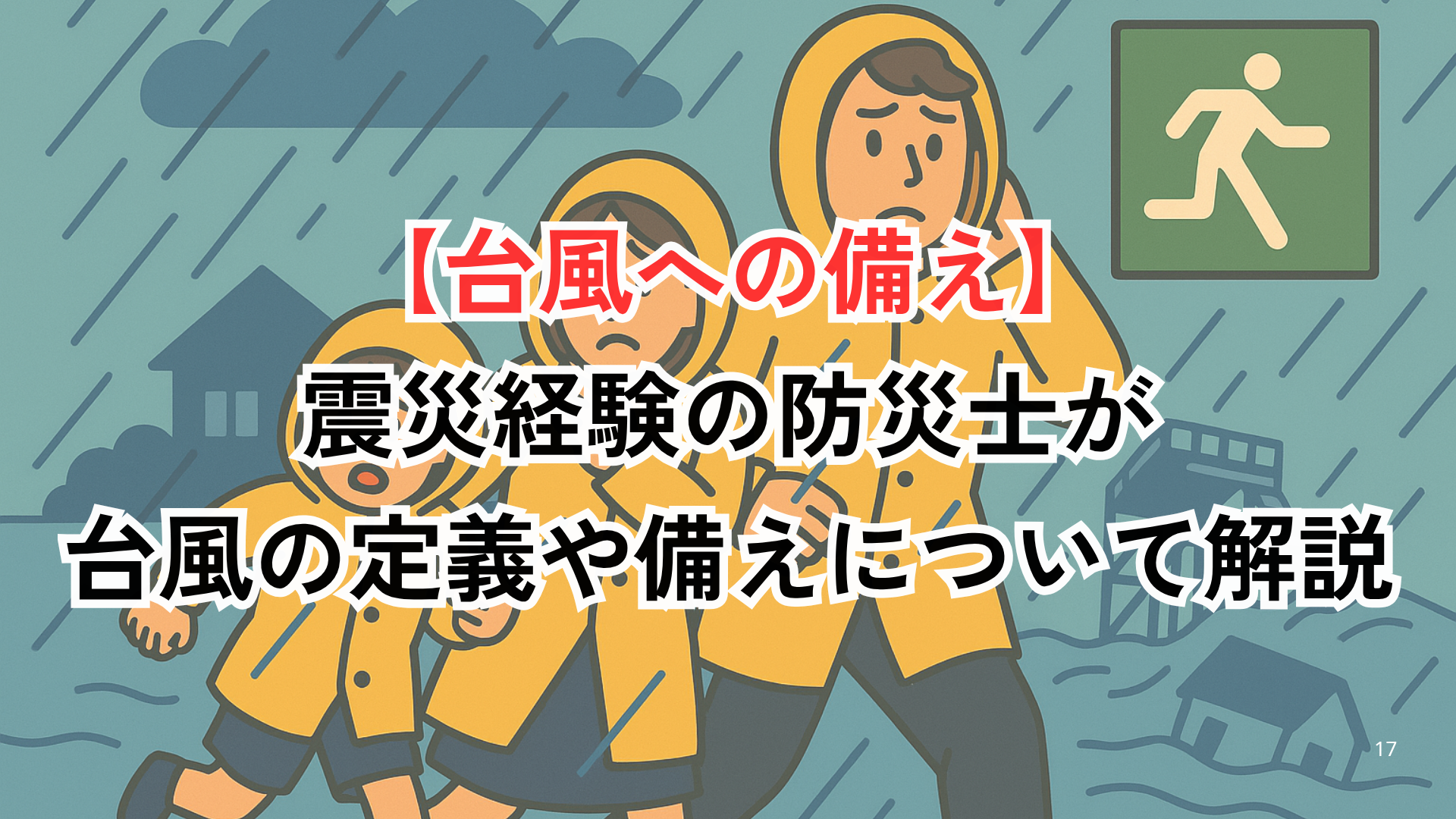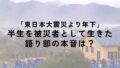黒潮町の特産品と南海トラフとの関係性について
皆さんこんにちは!
今回は高知県黒潮町について紹介したいと思います。
高知県黒潮町は海に面した町です。そして海に近い方は平野が広がっており、海から離れると山になってくるといったような地形です。
私が東日本大震災前に住んでいた釜石市片岸地区と似たような地形となっております。
海に近いことで漁業が盛んな町でもあります。
特に「カツオ」が有名です
私がよくお世話になっている「民宿おおまち」のお父さんも昔は漁師だったそうです。カツオ漁で東北の方まで行っていたと仰っていました。
民宿「おおまち」について ⇒ https://kuroshio-kanko.net/info/oomachi
そこでまさかの釜石にも降りたことあるそうで高知県の方と釜石トークが出来るとは思いませんでした。
民宿で頂いたカツオの藁焼きは絶品でした!
地元の大方高等学校の生徒さんで製作した「カツオバーガー」も頂きましたがとても美味しかったです。
カツオバーガーについて ⇒ https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/kikaku-osirase/37
そんなカツオ漁で有名な高知県黒潮町ですが、海が近い分自然災害の危険性も高いです。
特に「津波」の危険性が全国でもトップクラスです。
平成24年3月31日に、南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高の推計が、国(内閣府)から第1次報告として34.4mの津波が到達すると発表されました。
東日本大震災で釜石を襲った津波の約3倍です。
そして津波の予測到達時間も約10分とかなり早い方です。
ここまで圧倒的な数字で危険性を発表されたら誰しもが諦めると思います。「自分の町がどうやっても津波に飲み込まれてしまうのだ」「南海トラフ地震が起きたら助からないんだ」と思うはずです。
しかし、この町は生きるとことを諦めませんでした。
黒潮町の防災目標
絶望的な数値で被害を予測された黒潮町は諦めずに「津波に備えよう」と防災に力を入れるようになりました。
黒潮町が掲げた防災の目標は「防災を地域文化として育む」です。
「日常生活の中で防災に落とし込める分野を探すこと」や「これから始める防災を日常化レベルまで上げていくこと」を目指して活動することで「防災」を地域文化として地域住民に浸透していくといった内容です。
確かに普段の生活や仕事内容に「防災」を取り入れることで町全体として防災への関心が高まっていくと思います。
実際に私が当時避難した時に通っていた釜石東中学校も「地震が来たらまずあの避難場所まで避難」というのを全校生徒が理解して実際に一人でも避難できるレベルまで当たり前のことになっていました。
だからこそこの目標は私個人的には大変素晴らしいと思います。
津波避難タワー
34.4mの津波が10分程で到達してしまうと言われた黒潮町ですが、大きな問題は「高齢者の避難」でした。高齢者の方は「走って、遠くの、高い場所へ避難する」ということが体力的な面で難しい部分ではあります。
そこで取った解決策は「近くに高い避難場所を作ろう」という狙いで建てられた「津波避難タワー」となります。坂道や山など徐々に高い場所へ登るのではなくて、すぐ近くの高い場所に登っていくことを「垂直避難」といいます。
走って遠くへ行けない方が近くの高い場所に避難すること可能にした避難場所が津波避難タワーです。
私が実際に見に行った収容人数230人の黒潮町佐賀地区の避難タワーの大きさは22.0mで、中では中長期的に避難所生活が出来るように毛布や非常食を備えてある施設となります。

地震発生時は電気が停止する恐れがある為、エレベーターはありませんが、階段を上がるだけでかなり高い位置まで避難することが可能となっています。
黒潮町には高さにバラつきはありますが全部で6箇所の津波避難タワーが建設されています。
このように高齢者の体力面や津波到達時間が早い地域には向いた避難場所となっております。
このような垂直避難場所は皆さんの地域にも存在します。例えば近くのビルやマンションなどです。是非ハザードマップを見て自分の家の近くに垂直避難が可能な施設があるか確認して下さい。
防災教育プログラム
小学生の時から防災教育を当たり前に取り入れることで、大人になった時に「防災知識が多い成人」になり、これから生まれてくる世代にも防災教育を継続して取り入れることで全世代が防災を日常に落とし込んでいる町にします。
小学生、中学生、高校生も防災教育にかなり熱心な学校が多いのが黒潮町の魅力でもあります。
例えば小学生は京都大学の防災を専門にしている教授に「外国人と一緒に避難する場合はどうしたらいいのか?」をテーマに授業をして頂いたり、高校生は一日防災授業の日を設けて、午前中に避難訓練、午後は避難所になっている自身の高校で避難所運営の訓練をしたりなど私が学生時代に行っていた防災教育よりも質の高い教育をやっています。
その中で大方高等学校は防災教育だけではなく越境入学を受け入れて地域に根付いた様々な活動を授業に取り入れて「地域創造コース」として一つの科として生徒を受け入れています。
自然豊かな場所で自分の目標を持って勉強したい方は是非オススメです!
高知県立大方高等学校ホームページ ⇒ https://www.kochinet.ed.jp/ogata-h
地元大工の参画
生業を「防災」に取り入れようということを目的に地元大工の皆さんに協力して頂き、町内登録工務店の耐震教室や耐震診断修了者対象の個別相談会、耐震事業個別訪問などを実施しています。
地域で働いているプロの方々の事業に「防災」を取り入れていく姿勢は仕事から町の防災を強化できるので素晴らしい初案だと思いました。
缶詰製作所によるポジティブ事業
34.4mの津波が来ると言われた黒潮町でネガティブな情報をポジティブに捉えて「防災事業」に変えた事例があります。それが黒潮町缶詰製作所による防災缶詰です。
こちらは以前私のこちらの記事でも取り上げましたがお洒落なデザインで味もかなり美味しかったです。
ロゴに34.4mの浸水深から取って「34M」と書いて黒潮町は防災に対して様々な角度からアプローチを掛けていることを象徴した商品となりました。
まとめ
高知県黒潮町は自然がとても美しい町です。「町のほとんどが津波に飲み込まれる」と言われて誰もが諦めるような現状でも腐らずに防災対策として「思想」から変えていくスタイルで防災文化が徐々に色濃くなってきた黒潮町。今後もどのような防災活動を取り入れて進めていくのか期待しています。
個人的にとても綺麗な町なので是非プライベートな旅行でも足を運んで下さい。