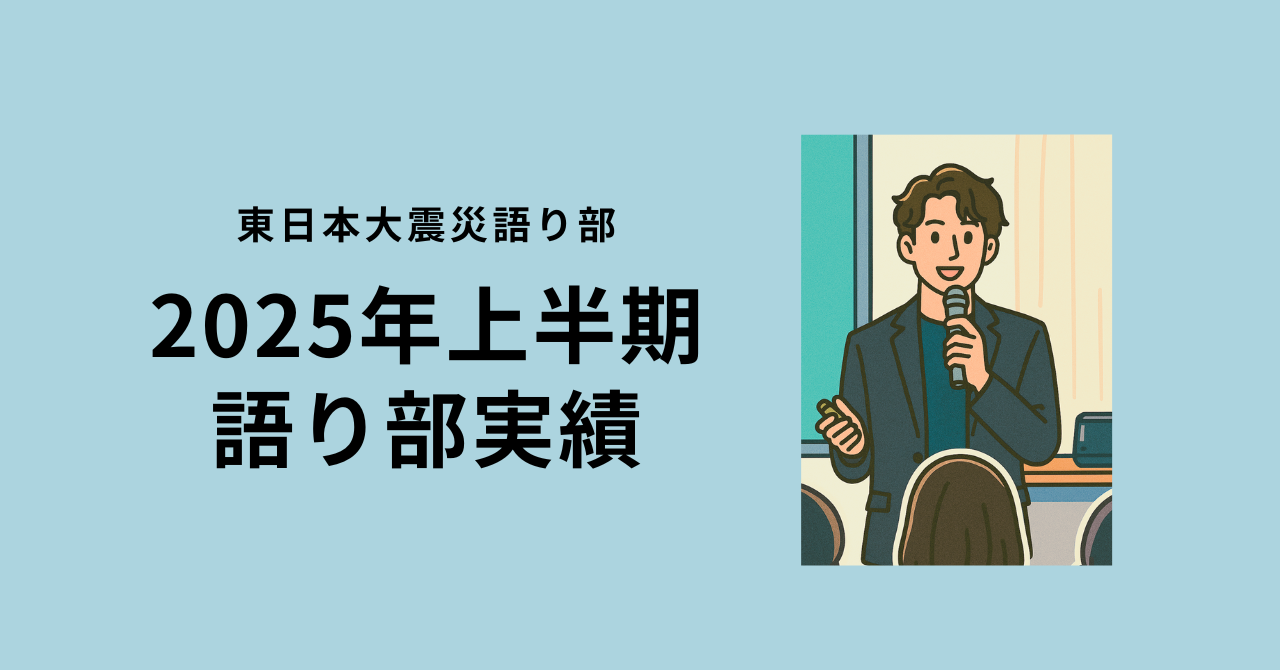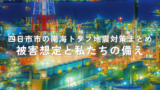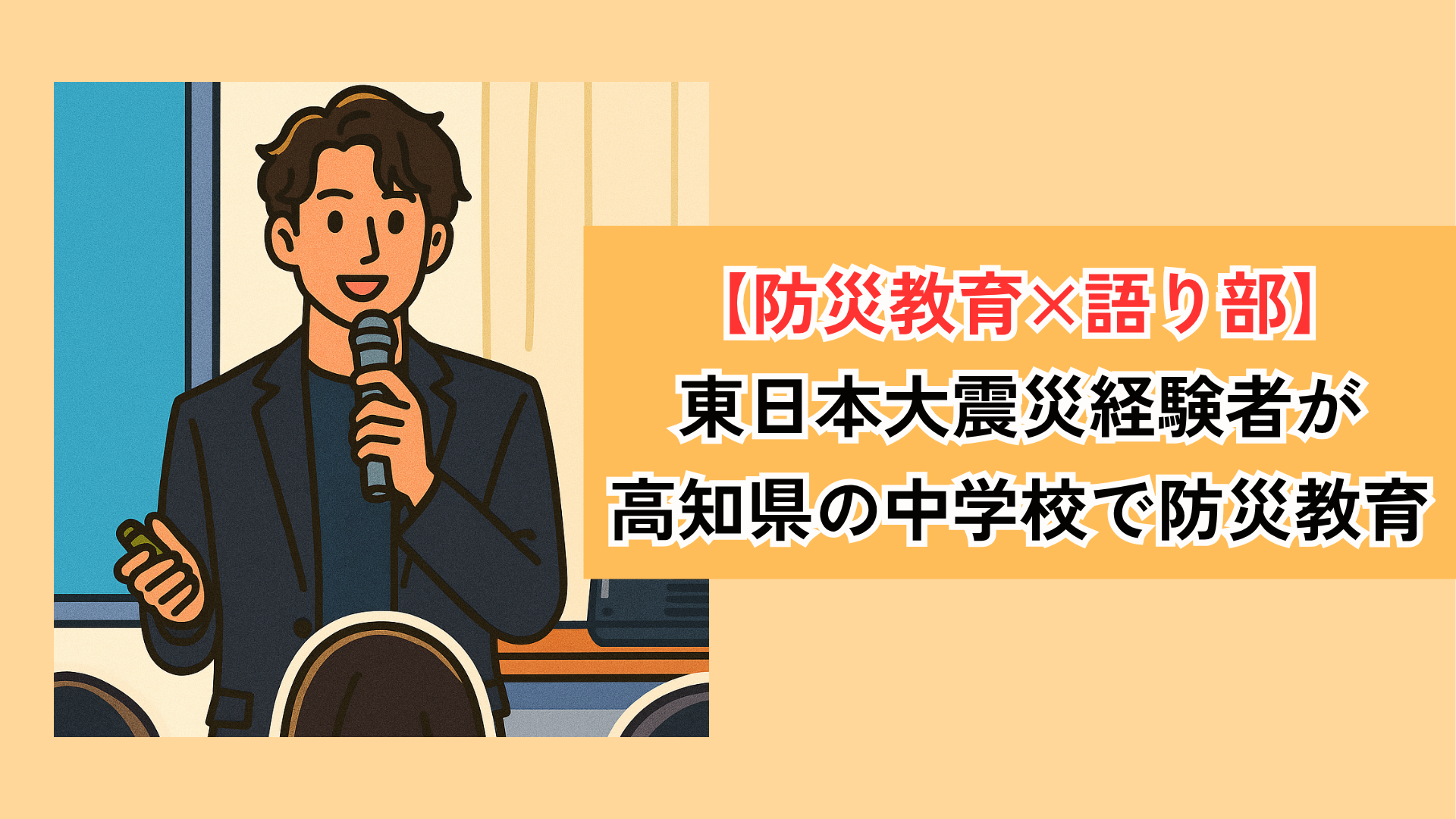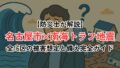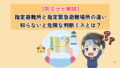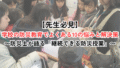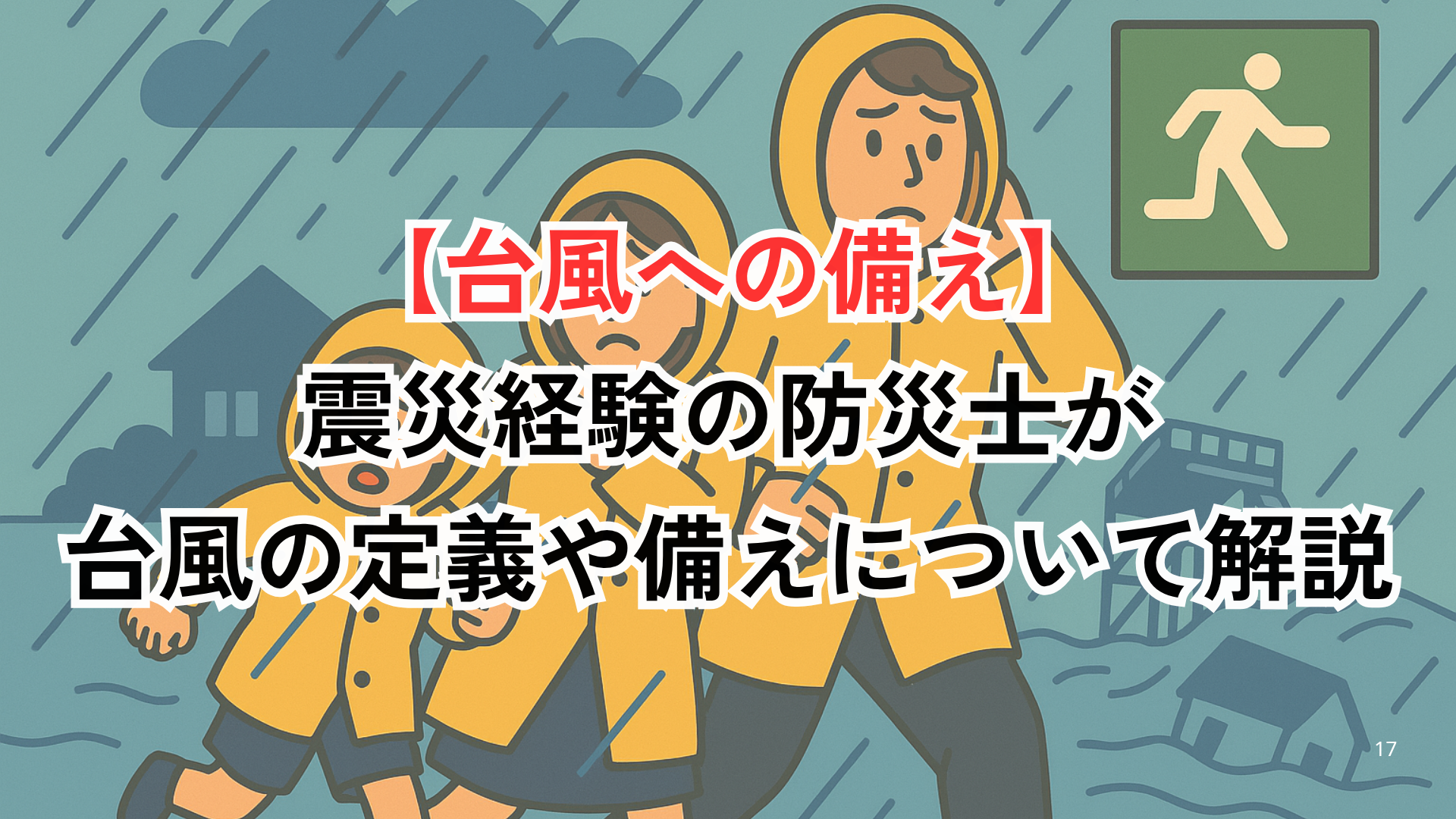語り部活動一覧
- 高知県黒潮町「大方人権まつり」 2月1日
- 三重県羽津中学校防災授業 3月7日
- 静岡県浜松市福祉交流センター 防災セミナー 3月9日
- 高知県黒潮町立佐賀中学校 防災授業 4月21日
- 愛知県立名古屋商業高等学校 「人生設計×防災」講師 5月19日
- 静岡県浜松市福祉交流センター 「三陸&東海 防災フォーラム伝 in東海」6月7日
高知県黒潮町「大方人権まつり」
2025年最初の語り部は毎年お世話になっている高知県黒潮町の「大方人権まつり」でした!
大方人権まつりとは「差別などがなく人間誰にでも人権が存在しているよ」という想いを音楽やアート、子供たちの人権に対する発表会などを通して発信していくイベントとなります。
私はその場で「震災で生きることを諦めないで」というテーマで語り部をしました。テーマ選定の理由は「高齢者が多い町は避難放棄を考えている人が多いから」です。
この黒潮町は南海トラフ地震で34mの津波が来ると予測された町です。高齢者も多く、避難放棄者が他の町と比べて多くなるのではないかと不安視されていました。行政や地元の企業、学校の生徒さんも活発的に避難を呼びかけるように防災訓練に地域住民を巻き込んで行ったりしていますが、実際に経験した方のお話を聞かせて頂きたいとお声がけを頂きました。
普段は60分くらいでお話をしますが今回は90分頂いたので普段は話せないような多くの事をお話しさせて頂きました。また地元・岩手県のテレビ局も密着で取材して頂いたのでかなり思い出に残っている語り部となりました!
三重県羽津中学校防災授業
三重県羽津中学校での2時間に及ぶ防災授業を行いました。三重県の学校ではこちらが初めてです。
羽津中学校での語り部ではなんと「当時一緒に津波から避難した中学校の先生とコラボ語り部」をしました!
先生とは以前も愛知県江南市の行政に対してコラボで語り部をしましたがその時は前半・後半で分かれてそれぞれのお話をするという形でした。しかし今回は2人で同じテーマに対してキャッチボールするような感覚で当時の様子を語っていくスタイルに変更しました!
同じ場面でも生徒と先生の状況や心境も違います。防災授業の始め方と進め方、震災当時の状況や心境、学校再開の方法、再開した後の学校生活のストレスも「子供と大人」「生徒と先生」は変わってきます。学校の防災授業としてはかなり有意義な語り部が出来たと思いました!
下記リンク先から「生徒×先生のコラボ語り部」を依頼できます!是非よろしくお願いいたします!
静岡県浜松市福祉交流センター 防災セミナー
初めての静岡県での語り部活動は浜松市でした!
今回の語り部は防災に関して有名な方々にお誘いを頂いて実現いたしました。
日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 副委員長でもある 永野 海 様
浜松市防災学習センター 副センター長 原田 博子 様
お二方をはじめとした防災学習センタースタッフの方々のご縁により、浜松市で語り部を行うことが出来ました。
羽津中学校で一緒に語り部をした先生と当時一緒に避難をした先輩の目の前での語り部でしたが途中で伝えたい想いが込み上がってしまい、もともと話す予定では無かったことをお話ししました。それは「家族と再会」したときのお話です。私はこの瞬間に家族を大切にしようと本気で思えました。その時の想いをどうしても伝えたいと想い、言葉にしました。
その後は永野先生と「釜石の出来事」当事者3人を交えてトークセッションを行いました。同じ地域に住んでいても考えていること、14年間の苦労や考え方の変化はそれぞれで違いました。また新しい視点を持つことができたのでかなり有意義な時間でした。


高知県黒潮町立佐賀中学校 防災授業
高知県黒潮町立佐賀中学校で行う語り部は2度目です。
1度目は学校で行いましたが今回は久しぶりのリモート語り部となりました。
もともと黒潮町は防災意識が高い町で、佐賀中学校も1度目の語り部のあとに「下校時の避難訓練」を行っておりました。なかなか下校時に避難訓練をする学校は多くはありません(少なくとも愛知県では聞いたことがないです…)
今回の語り部では「中学生が地域住民に対して行える防災アクション」についてを多めにお話ししました。
私が中学生の時に行った活動の一つで安否札作成という活動をしていました。
安否札とは避難時に玄関に置くor掛けることで「この家の人は避難しています」と一目で分かるような目印となる札です。実際に安否札を作成して、夏休みに鵜住居地区の各世帯に配布したものが東日本大震災の時に活躍した事例がありました。安否札があることで「消防団などの捜索者が住民を探す時間を削減できる」=「避難時間を確保できる」という効果になります。
実際に佐賀中学校の生徒さんは私の語り部の後に安否札を作成して地域住民に配布して回ったそうです。
ちなみに「中学生×地域住民」が防災アクションを取ることで
- 町全体の防災意識の向上
- 中学生の防災活動を応援してもらえる(学生に好影響)
- 中学生と地域住民の繋がりが強くなり、避難時に声掛けしやすい
などの効果が挙げられます。ですから、学生が地域住民のために防災活動をすることはとても大切になってきます。
愛知県立名古屋商業高等学校 「人生設計×防災」講師
以前からお世話になっている先生の方が転勤して、授業の一環で「人生設計×防災」について講師をして欲しいと依頼があり、初めてのテーマで語り部をしました。
人生の大きなポイントはざっくりですが以下の通りです。
- 就職&進学(地元を離れて、知らない町で一人暮らしを始めるかも)
- 結婚(家族が出来て同棲を開始。大人2名以上での共同生活がスタート)
- 妊娠&出産(妊婦の場合は病院選びや体調管理が重要。出産後は家族が増える)
どれも共通して言えることは「生活環境が変わる」です。特に住む場所が変わると思います。
一人暮らし、大人2人の同棲生活、子供が出来て一軒家を建てたりと住居は変わる可能性が高いです。
私は最も効果的な防災アクションは「被害の少ない場所に住む」ことだと思います。まず住む場所が無事だった場合、ストレスの多い避難所生活をしなくて済みます(1週間以上の備蓄は必須になります)
災害後の生活も仮設住宅などではなく、自分の家で過ごすことが出来ます。
なにより1日の半分を過ごすのが家です。つまり災害時にいる場所の可能性が高いのも「家にいる」時になります。
それならば想定被害が少ない、津波が到達する可能性が低い、液状化の恐れがない、土砂崩れが起きそうな山などが近くに無いなどの条件が揃っている場所に住むことはかなり重要になってきます。
先程挙げた人生の大きなポイントは「住居を変更する」可能性が最も高いタイミングです。
その際に是非、災害リスクの低い家に住むことも「人生設計×防災」であると伝える授業となりました。
静岡県浜松市福祉交流センター 「三陸&東海 防災フォーラム伝 in東海」」講師

こちらのチラシに書いてある防災イベントで語り部をしました。昨年は東京で行いましたが今年は初めて浜松で開催しました。
午前中は千葉先生の「東日本大震災後の防災学習の取り組み方や効果について」
西方先生の「自然災害との付き合い方と企業防災の取組み事例」などについてお話がありました。
元学校の先生とBCP策定の先生がお話しする内容はそれぞれの防災観点や意識が違くて、新たな視点を持たせて頂きました。
私は90分頂いたので当時の様子や防災学習の内容、震災後の生活について赤裸々にお話ししました。
その中でハザードマップと避難訓練について大切な点と疑うべき点についてお話をさせて頂きました。
終わった直後にワークショップで各グループで「自分の職場や家の周りにどんなリスクがあって、課題はあるけど改善できない悩みの理由」などを話し合ってもらいました。
ワークショップはかなり熱中していました。保育士としての悩み、高速道路をよく利用する人の悩み、地域で防災訓練の悩みなど多くの不安が挙がりましたがそれを参加者それぞれの観点で改善策を見出していくワークショップの時間は大変有意義でした。
まとめ
2025年上半期は合計で6回の語り部を行いました。
多くの方がに依頼をして頂き大変嬉しく思います。
語り部をする中で多くの方々と出会い、交流を深めていくことで新しい防災の視点を得ることで、新しい防災の発想や知識が増えていくことがあります。
その結果、語り部としての話の深みがました気がしています。
- 実際に震災や津波を経験した人の話を聞いてみたい
- 学校の防災授業の内容を悩んでいるけど何したらいいか分からない
- 自主防災組織として防災活動の講師を呼びたいけど誰が適任か分からない
- 地域住民の防災意識向上や悩みを解決したい
南海トラフ地震が起きる前にもっと多くの場所で語り部をしたいです。
是非語り部の依頼をお願い致します。
現時点でブログを通して依頼をして頂いた方が2団体あります。
お問合せから依頼の連絡or相談を宜しくお願いいたします!