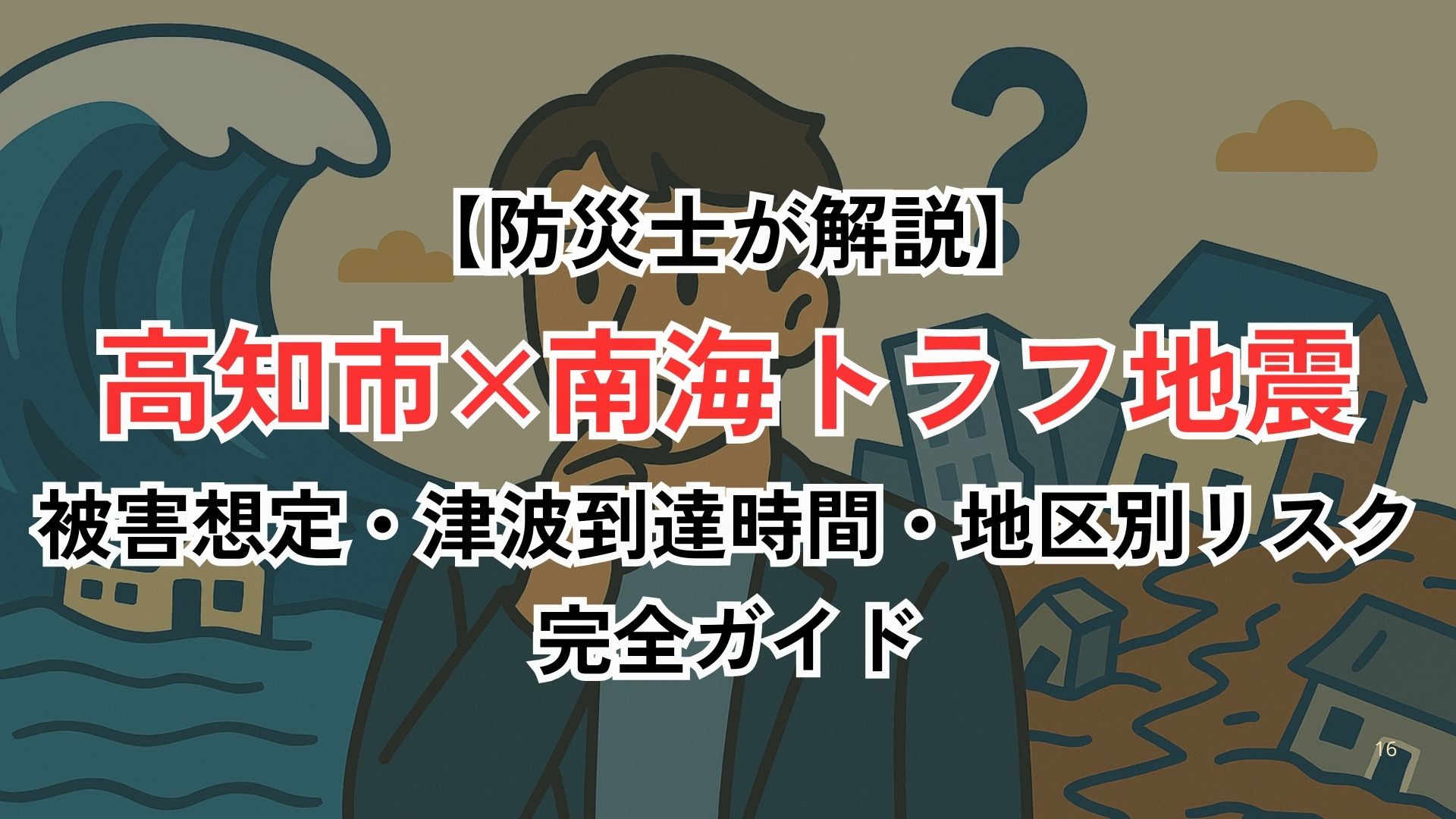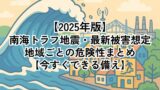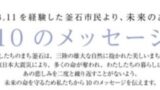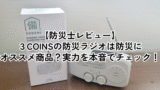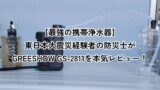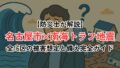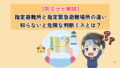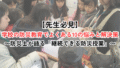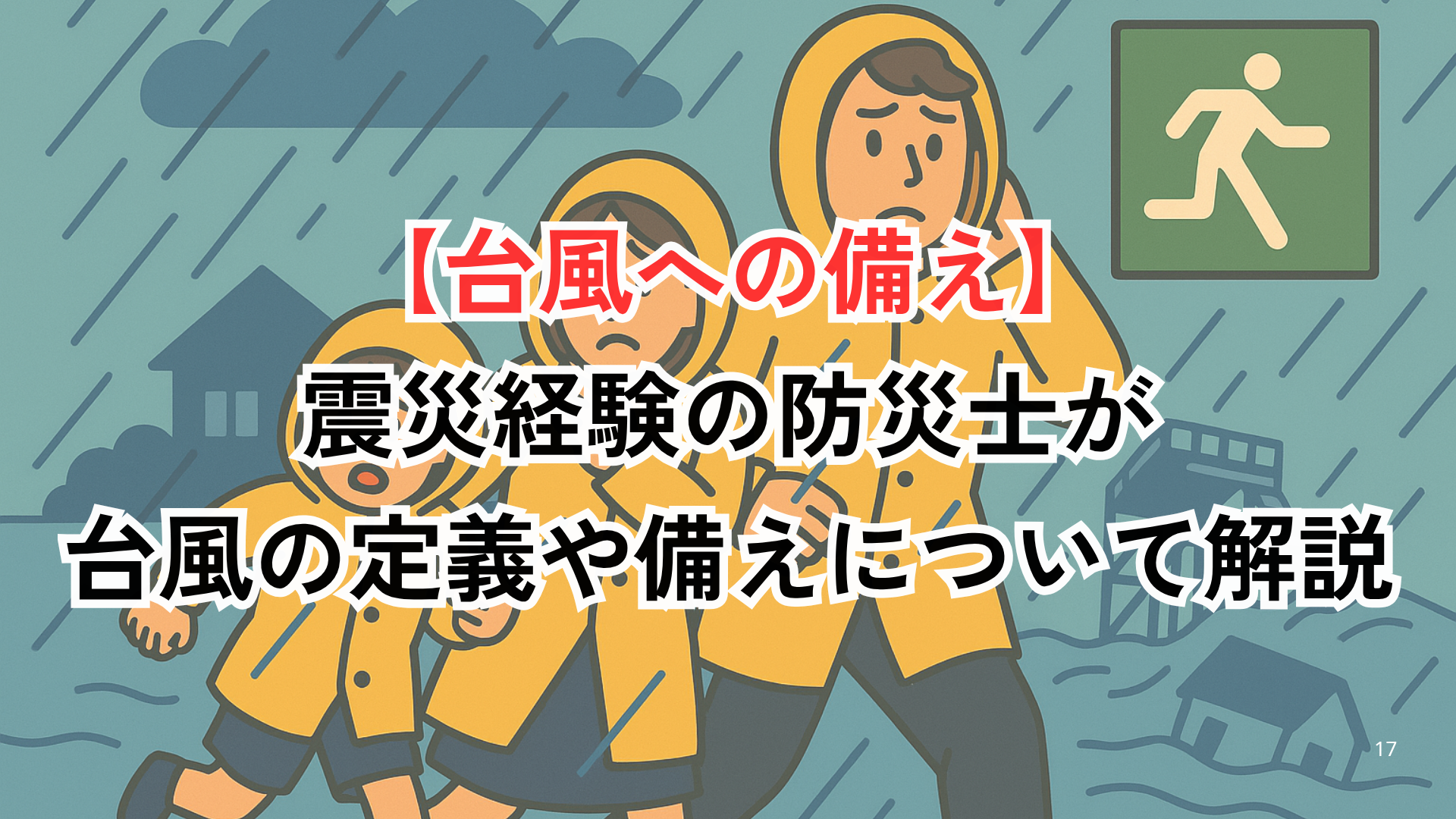第1章 高知市と南海トラフ地震:なぜ今知るべきなのか
「もし南海トラフ地震が起きたら、高知市はどうなるのか?」
これは高知市に暮らす人はもちろん、観光や仕事で訪れる人にとっても重要なテーマです。
南海トラフ地震は、30年以内に70〜80%の確率で発生すると言われる大規模地震です。
震源域に近い高知市は震度7の揺れと最大20m級の津波が想定されており、日本国内でも最も被害が深刻になる可能性がある都市のひとつです。
この記事では、高知市における南海トラフ地震の被害想定や過去の地震被害の歴史をわかりやすく解説します。
そして、なぜ今「備え」が必要なのかを掘り下げていきます。
- 南海トラフ地震とは?
- 過去の南海トラフ地震と高知市
- 高知市における被害想定
- なぜ今、防災を学ぶ必要があるのか
- 高知市民・来訪者が準備すべきこと
- この記事でわかること
- 高知市における南海トラフ地震の被害想定表
- 高知市の津波到達時間と避難情報(地区別+主要施設)
- 高知市地区別の浸水・被害想定
- 地区ごとの避難のポイント
- 避難のポイント
- 地区別避難シナリオ表
- 避難行動のチェックリスト
- 高知市家庭向けおすすめ防災備蓄リスト
- 家庭での備えのポイント
- 高知市の避難所収容人数と予想避難人口の比較
- インフラ復旧の目安と生活支援体制
- 高知市 防災訓練 実態と課題(地区別)
- 医療機関の機能別・地域別体制
- 医療情報の収集・伝達体制
- 現地医療対策
- 後方医療対策
- 「釜石の奇跡」当事者が伝えたいこと
南海トラフ地震とは?
南海トラフ地震とは、駿河湾から九州沖にかけて広がるプレート境界で発生する巨大地震の総称です。
フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に、ひずみが限界まで蓄積され、一気に解放されることで発生します。
この地震は約100〜150年周期で繰り返されており、古くから「必ず起きる地震」として恐れられてきました。
政府の地震調査研究推進本部によれば、今後30年以内の発生確率は70〜80%とされています。
つまり、「いつ起きても不思議ではない」段階にあるのです。
過去の南海トラフ地震と高知市
高知市は南海トラフ地震のたびに大きな被害を受けてきました。
その歴史を振り返ると、今後起きる地震のイメージが具体的に見えてきます。
- 1707年 宝永地震(M8.6〜8.7)
土佐湾沿岸には10mを超える津波が襲来。高知平野は広範囲で浸水しました。 - 1854年 安政南海地震(M8.4)
高知城下町に甚大な被害。浦戸湾や沿岸部に大津波が押し寄せました。 - 1946年 昭和南海地震(M8.0)
市街地は震度6前後の強い揺れで建物が倒壊。津波が浦戸湾から侵入し、市街地や港湾に甚大な被害をもたらしました。
このように、高知市は歴史的に「津波常襲地域」であり、地震と津波がセットで発生してきたことがわかります。
そして前回の昭和南海地震から80年近くが経過しており、周期的に見ても次の地震が迫っているのは間違いありません。
高知市における被害想定
高知県と高知市が発表している最新の被害想定によれば、南海トラフ地震が発生した場合に予測される影響は次の通りです。
- 最大震度:震度7(市内全域で強烈な揺れが想定)
- 津波の高さ:最大20m超(浦戸湾・桂浜周辺)
- 津波到達時間:地震発生から数分〜10分程度
- 死者数:最悪シナリオで数万人規模
- 家屋全壊・焼失:約4万棟以上
- ライフライン停止:電気・水道・ガスの長期停止が想定
特に高知市の中心部がある高知平野は標高が低く、津波が奥深くまで侵入しやすい地形です。
そのため、地震後に「避難しよう」としても、津波到達までの時間が短く、逃げ遅れる危険性が非常に高いと指摘されています。
なぜ今、防災を学ぶ必要があるのか
「南海トラフ地震は必ず起きる」
そう言われながらも、多くの人は「まだ大丈夫」と思いがちです。
しかし研究では、プレート境界におけるひずみの蓄積が限界に近づいていることが報告されており、発生はいつ起きても不思議ではありません。
特に高知市は、全国で最も津波被害リスクが高い都市の一つです。
津波が到達するまでの時間が短いため、「事前の備え」こそが命を守る唯一の手段となります。
実際に東日本大震災も発生する前は「近い将来必ず起きる」と言われていましたが私は信じていませんでした。
自分が生きている間に大災害の被害を受けるはずがない
そう思っていた矢先に大地震が起きました。
しかし、助かった理由は「被害想定を把握したうえで、さらに被害を予想して備えていたから」です。
高知市民・来訪者が準備すべきこと
では具体的に、私たちは何を準備すべきなのでしょうか。
防災の専門家や行政が推奨しているポイントは以下の通りです。
- 自宅や職場の最寄り避難所を確認する
- 避難ルートを実際に歩いて確認しておく
- 家族で連絡方法や集合場所を決めておく
- 非常持ち出し袋を準備(水・食料・充電器・薬など)
- 地域の避難訓練に参加して実践的に学ぶ
これらは一見シンプルに見えますが、実際に「やっているか」となると、まだまだ多くの人が不十分です。
大切なのは「地震が来たらどう動くか」を具体的にイメージしておくことです。
この記事でわかること
本記事では、この第1章で「なぜ高知市が南海トラフ地震を学ぶ必要があるのか」を解説しました。
第2章以降ではさらに詳しく、
- 高知市の地区別の被害想定
- 高知市全域の避難所・避難施設の情報
- 避難シナリオの具体例
- 家庭や職場での防災対策
- 「釜石の奇跡」の当事者の経験談を学べる
を紹介していきます。
「知っている」だけで助かる命がある。
次の章では、高知市の被害想定をさらに掘り下げていきましょう。
第2章 高知市における南海トラフ地震の被害想定
第1章では「なぜ高知市にとって南海トラフ地震が大きな脅威なのか」を歴史や背景から解説しました。
この第2章では、実際に高知市で想定されている被害の具体像について見ていきます。
南海トラフ地震が発生すると、高知市には「強烈な揺れ」と「巨大津波」がほぼ同時に襲いかかります。
さらにその後も、火災やインフラの停止、長期的な避難生活など、さまざまな二次被害が発生することが想定されています。
高知市における南海トラフ地震の被害想定表
| 被害項目 | 想定内容(高知市) | 備考・解説 |
|---|---|---|
| 震度 | 最大震度7 | 市内全域で強い揺れ。木造住宅中心に倒壊多数 |
| 津波 | 最大20m超 | 浦戸湾・桂浜周辺で特に高い。市街地に広く浸水 |
| 津波到達時間 | 最短数分〜10分 | 揺れたらすぐ避難が必要 |
| 浸水範囲 | 市街地の大部分 | 高知平野は低地が多く広域水没 |
| 建物被害 | 全壊:約3万棟、半壊:約5万棟(想定) | 木造住宅中心に甚大な被害 |
| 死者数 | 数千人規模(想定) | 避難遅れや津波により多数発生の恐れ |
| 負傷者数 | 数万人規模 | 倒壊・津波・火災による |
| 火災 | 数百件の出火想定 | 消防活動困難、住宅密集地で延焼拡大 |
| 避難者数 | 数十万人規模 | 市全体人口の過半数が一時避難の可能性 |
| 断水 | ほぼ全域で断水 | 復旧に数週間〜数か月 |
| 停電 | 広域停電 | 数週間規模で復旧見込み |
| ガス停止 | 都市ガス供給全面停止 | 復旧に1〜2か月以上 |
| 通信 | 携帯・固定電話ともに不通 | 数日〜数週間、情報入手困難 |
| 交通 | 道路・橋梁・鉄道が寸断 | 孤立集落が発生の恐れ |
| 避難所生活 | 数万人が長期避難 | 水・食料不足、感染症リスク増大 |
想定される地震の規模と揺れ
政府の中央防災会議や高知県の被害想定によると、南海トラフ地震はマグニチュード9.0級の超巨大地震となる可能性があります。
- 高知市内の想定震度:最大震度7
- 家屋の全壊率:木造住宅を中心に大幅に上昇
- 建物の倒壊による死者:多数
特に高知市中心部は木造住宅密集地が多く、揺れによる家屋の倒壊が大きなリスクです。
また、学校や病院など公共施設も被害を受ければ、避難や医療対応が滞る恐れがあります。
津波被害の想定
高知市にとって最も深刻な脅威は、揺れの直後に押し寄せる津波です。
- 最大津波高:20m超(桂浜・浦戸湾周辺)
- 市街地への津波侵入:高知平野に奥深くまで浸水
- 浸水範囲:市街地の大部分、特に低地は全域水没の可能性
- 津波到達時間:最短数分〜10分程度
高知平野は川が多く、津波が遡上しやすい地形です。
津波は海からだけでなく、浦戸湾や河川を通じて市街地に侵入するため、避難が遅れると逃げ場を失う危険性があります。
過去の昭和南海地震でも津波は浦戸湾を通じて市街地に達しました。
今回想定されている津波はそれをはるかに超える規模であり、「揺れたらすぐ避難」が命を守る唯一の行動です。
火災・延焼のリスク
大規模地震では、電気・ガス設備の損傷や倒壊した建物からの出火によって、火災が同時多発的に発生します。
- 出火件数:数百件規模
- 延焼範囲:市街地の木造住宅地で甚大な被害
- 消防活動の制限:道路損壊・津波浸水で消火困難
特に高知市中心部の住宅密集地は「火災危険地域」に指定されています。
もし地震直後に火災が起きても、消防隊の出動は道路の損壊や浸水で大きく妨げられます。
つまり「自力で逃げる」ことが最優先となります。
インフラ・ライフライン被害
地震と津波に続いて市民生活を直撃するのが、ライフラインの停止です。
- 電力:発電所・送電設備の損壊で広域停電。復旧まで数週間〜数か月。
- 水道:浄水場・配水管の損傷で断水。飲み水の確保が最優先課題。
- ガス:都市ガス供給は長期停止。復旧に1〜2か月以上。
- 通信:携帯電話回線の輻輳・基地局被害で連絡が困難に。
- 交通:道路の崩落、橋梁破損で市街地の孤立化。
特に水と通信の停止は、避難生活に直結する大問題です。
飲料水・トイレ・情報入手手段をどう確保するかが、被害後の大きな課題となります。
二次被害と生活への影響
南海トラフ地震では、揺れや津波だけでなく、長期的に生活を脅かす二次被害が予想されています。
- 医療崩壊:病院の被災やスタッフ不足により、治療が滞る
- 物流の停止:道路や港湾の破壊で食料・物資が届かない
- 避難所の過密化:数万人規模が避難し、衛生・プライバシー問題が深刻化
- 感染症リスク:避難所での集団生活に伴うインフルエンザ・胃腸炎・コロナなど
- 経済被害:観光業・漁業・商業施設の被害で長期的な地域経済の停滞
「地震発生直後を生き延びること」と同じくらい、「その後の生活をどう持ちこたえるか」も重要な課題です。
被害想定から見える課題
こうした被害想定をまとめると、高知市における課題は大きく3つに集約されます。
- 津波からの迅速な避難ができるか
揺れの直後、数分以内に避難行動をとれるかが生死を分けます。 - 避難所や高台の収容力・アクセス
市街地の人口に対して避難可能な施設や高台が足りるのか。
道路が寸断されれば避難が困難になる地域もあります。 - 長期的な生活再建への備え
水・食料・医療などインフラが数週間以上停止したとき、地域と家庭でどう持ちこたえるか。
これらの課題を踏まえると、「行政任せ」ではなく、一人ひとりが主体的に準備することが不可欠です。
まとめ:高知市の被害想定が教えてくれること
第2章では、高知市で想定される南海トラフ地震の被害を具体的に解説しました。
- 強烈な揺れによる建物被害
- 数分で到達する巨大津波
- 市街地での火災・延焼リスク
- 電気・水道・ガス・通信の長期停止
- 避難所生活や医療崩壊など二次被害
これらはすべて、科学的根拠に基づいて想定されている現実的なシナリオです。
そして地域ごとのリスクを理解するために用いるのがハザードマップです。
ハザードマップを確認することで災害リスクの内容と範囲を確認することができます。
高知市で出しているハザードマップや国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」などもあります。
こちらの記事ではハザードマップポータルサイトの使い方をまとめています。是非ご覧ください。
そして最も重要なのは、「南海トラフ地震は必ず起きる」という前提に立ち、今から準備を始めること。
この記事を読んでいる今この瞬間から、できることを一つずつ積み重ねていくことが、未来の命を守ります。
高知市の津波到達時間と避難情報(地区別+主要施設)
地区別津波到達時間(浸水深30cm到達までの目安)
| 地区名 | 到達時間の目安 | 備考・特徴 |
|---|---|---|
| 横浜 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 三里 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 大津 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 介良 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 高須 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 朝倉 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 春野 | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 中心部(はりまや橋、高知駅周辺) | 40–60分 | 内陸部、避難所が多い |
| 浦戸湾口(種崎) | 5–10分 | 沿岸部、湾内増幅リスクあり |
| 高知空港周辺 | 40–60分 | 内陸部、避難所が多い |
主要施設・観光地の津波到達時間(浸水深30cm到達までの目安)
| 施設名 | 到達時間の目安 | 備考・特徴 |
|---|---|---|
| 桂浜 | 5–10分 | 沿岸部、観光地 |
| 高知新港 | 5–10分 | 沿岸部、物流拠点 |
| はりまや橋 | 40–60分 | 市中心部、観光地 |
| 高知駅 | 40–60分 | 市中心部、交通拠点 |
| わんぱーくこうち | 40–60分 | 市中心部、観光地 |
| 高知龍馬空港 | 40–60分 | 市外、交通拠点 |
避難行動のポイント
- 揺れを感じたら即座に避難:津波警報が出る前でも、揺れを感じたらすぐに高台や避難ビルへ避難してください。
- 徒歩での避難を優先:車での移動は渋滞や道路の冠水で困難になる可能性があります。
- 避難場所の確認:自宅や職場、学校などから最寄りの避難場所を事前に確認しておきましょう。
- 家族や地域での連携:避難時には家族や地域の人々と連携し、助け合いながら行動しましょう。
第3章 高知市の地区別被害想定と避難のポイント
第2章では高知市全体の被害想定を見てきました。
ここからは、高知市内の各地区ごとの被害リスクに焦点を当てます。
高知市は、山地・平野・沿岸地域が入り組んでおり、地区ごとに津波や揺れの影響が大きく異なります。
自分が住む地域の特性を知ることは、避難計画を立てるうえで非常に重要です。
高知市地区別の浸水・被害想定
以下は、高知市内の代表的な地区ごとの南海トラフ地震被害想定の表です。
津波浸水や避難所までの目安時間などを整理して、自分の地域でどのような備えが必要かが一目で分かるようにしています。
| 地区 | 想定震度 | 最大津波高さ | 津波到達時間 | 避難所数 | 避難時間の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央地区(高知市中心部) | 7 | 5〜10m | 5〜7分 | 20 | 5〜10分 | 平野部が多く浸水しやすい |
| 浦戸地区 | 7 | 15〜20m | 3〜5分 | 5 | 3〜5分 | 海に近く津波到達が非常に早い |
| 鏡地区 | 6強 | 3〜5m | 10分 | 8 | 5〜10分 | 河川沿いは津波遡上注意 |
| 朝倉地区 | 6強 | 1〜2m | 15分 | 6 | 10〜15分 | 山間部で津波被害は少ないが揺れに注意 |
| 土佐山地区 | 6弱 | 0m | — | 4 | — | 山間部、津波リスクなし、地盤揺れ中心 |
| 仁淀地区 | 6弱 | 0m | — | 3 | — | 山間部、津波リスクなし、避難は地震対策中心 |
| 春野地区 | 6強 | 2〜3m | 10〜12分 | 7 | 10分前後 | 平野部の一部が浸水、避難所まで早めに移動 |
- 津波到達時間
揺れを感じたらすぐに避難を開始する必要があります。浦戸地区のように数分で津波が到達する地域では、避難行動の迅速さが命を左右します。 - 避難所数
避難所の数は地区人口や面積に応じていますが、人数が多い地区では混雑する可能性があります。早めの避難が重要です。 - 避難時間の目安
自宅から避難所までの移動時間の目安です。標高が高い場所や川沿いなど、地形による違いもあります。
地区ごとの避難のポイント
中央地区(高知市中心部)
- 平野部が多く浸水リスクが高い
- 近くの高台や避難ビルへの迅速な避難が必要
- 道路損壊や渋滞で避難が遅れる可能性があるため、徒歩での避難ルートを事前確認
浦戸地区
- 海に近く、津波到達が非常に早い
- すぐに高台や指定避難所へ避難
- 高齢者や子どもは特に迅速な行動が必須
鏡地区・春野地区
- 河川沿いで津波が遡上する可能性あり
- 自宅の安全な場所から少しでも早く避難所へ移動
山間部(朝倉・土佐山・仁淀地区)
- 津波の心配はほぼなし
- 建物倒壊や地滑りなど地震揺れ対策が中心
- 避難所までの移動や断水・停電への備えが重要
- 揺れを感じたら、津波が想定される地域(平野部・沿岸部)では即座に高台や避難施設へ
- 津波の心配がない山間部では、まず建物被害を避ける安全行動
- 家族で集合場所や避難ルートを事前に決めておくことで、混乱を最小限にできる
次の第4章では、高知市全域の避難所リストと避難方法をさらに詳しく紹介します。
「自分の地区にはどこに避難すればいいのか?」を具体的に知ることができる章です。
第4章 高知市の避難所リストと避難方法
南海トラフ地震の被害想定を知ったら、次に重要なのは「どこに避難するか」です。
高知市は地区ごとに避難所が設置されており、津波や地震から身を守るための拠点になっています。
ここでは、地区ごとの避難所一覧と、避難所の標高、運営訓練の有無などをまとめた表を紹介します。
| 地区 | 避難所名 | 標高(m) | 避難所運営訓練 |
|---|---|---|---|
| 中央地区 | 高知市立愛宕小学校 | 追記予定 | 毎年3月、防災訓練あり(避難誘導・防災備蓄確認) |
| 中央地区 | 高知市立城西中学校 | 追記予定 | 年2回、避難訓練実施(避難経路確認・避難者数集計) |
| 浦戸地区 | 浦戸小学校 | 追記予定 | 隔年で避難所運営訓練(津波想定・高台避難) |
| 鏡地区 | 鏡小学校 | 追記予定 | 毎年避難訓練(避難誘導・備蓄確認) |
| 朝倉地区 | 朝倉中学校 | 追記予定 | 年1回、避難所運営訓練実施 |
| 土佐山地区 | 土佐山小学校 | 追記予定 | 防災委員会主催の避難訓練あり |
| 仁淀地区 | 仁淀小学校 | 追記予定 | 地域主導の避難訓練実施 |
| 春野地区 | 春野中学校 | 追記予定 | 毎年避難訓練あり(避難ルート確認・高台移動) |
よく「避難所」と「避難場所」を間違える人がいます。
その違いはこちらの記事で解説しています。是非読んでください!
避難のポイント
- 揺れを感じたらまず安全な場所へ移動
高知市の沿岸部は津波到達が数分以内なので、迷わず避難開始。 - 避難所までのルートを事前確認
道路が損壊する可能性があるため、徒歩での最短ルートを把握。 - 地域の避難訓練に参加
訓練を通じて避難所の場所や運営手順を確認しておくと安心。 - 家族と避難計画を共有
集合場所や避難ルートを話し合い、万一の時に混乱しないように準備。
次の第5章では、高知市での具体的な避難シナリオを解説し、
「自宅から避難所までどう行動すればよいか」をリアルにイメージできるようにします。
第5章 高知市における地区別避難シナリオ
第4章で避難所リストを確認したら、次は自宅から避難所までどう行動するかの具体的なシナリオです。
ここでは、地区ごとに想定される津波到達時間や避難時間、避難のポイントをまとめています。
地区別避難シナリオ表
| 地区 | 自宅から避難所までの目安時間 | 津波到達時間 | 避難開始タイミング | 避難のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中央地区 | 5〜10分 | 5〜7分 | 揺れを感じたらすぐ避難 | 平野部は浸水が早いので高台・避難ビルへ直行 |
| 浦戸地区 | 3〜5分 | 3〜5分 | 揺れと同時に避難開始 | 海に近く到達時間が短い。徒歩で高台へ急ぐ |
| 鏡地区 | 5〜10分 | 10分 | 揺れを感じたら即避難 | 河川沿いの浸水リスクに注意。川沿いは早めに離れる |
| 朝倉地区 | 10〜15分 | 15分 | 揺れを確認後、速やかに避難 | 山間部なので津波リスクは低いが建物倒壊に注意 |
| 土佐山地区 | 15分前後 | — | 揺れを感じたら安全な場所に移動 | 津波は心配なし。地滑り・倒壊への対応が中心 |
| 仁淀地区 | 15分前後 | — | 揺れ確認後に避難所へ移動 | 津波リスクなし。建物被害・停電への備えを優先 |
| 春野地区 | 10分前後 | 10〜12分 | 揺れを感じたら速やかに避難 | 平野部の一部が浸水するため、早めに避難所へ移動 |
- 避難開始タイミング
各地区で津波到達時間が異なるため、「揺れを感じたらすぐ避難」が基本です。
浦戸地区のように数分で到達する場所では、迷わず徒歩で高台へ直行。 - 避難時間の目安
自宅から避難所までの所要時間を示しているので、徒歩ルートや移動速度をイメージ可能。 - 避難のポイント
地区ごとの特性に応じた注意点をまとめています。
平野部や河川沿い、山間部でそれぞれリスクが異なるため、事前に把握しておくと安心。
避難行動のチェックリスト
- 揺れを感じたら迷わず避難
- 家族の集合場所や避難ルートを確認
- 津波の恐れがある地区は、高台や避難ビルを最優先
- 山間部は建物倒壊や地滑りに注意
- 徒歩で避難可能かどうかを事前に確認しておく
大きな揺れを感じたらまず避難をして下さい
100回避難して津波が来なくても、101回目で来るかもしれません。
釜石でも過去の大きな地震でも津波が来なかったという考えから、避難せずに津波に襲われた人が数多くいます。
「避難する必要がなかった」ではなく「避難したけど津波が来なくて良かった」と思ってください。
釜石市民が残したメッセージについて解説した記事があります。是非、大津波を体験した人達が残した言葉から感じ取ってください。
次の第6章では、高知市の家庭でできる防災準備や備蓄について詳しく解説します。
「自宅で何を準備すべきか」が明確になる章です。
第6章 高知市の家庭でできる防災準備と備蓄リスト
南海トラフ地震は、いつ発生するか予測できません。
高知市は沿岸部では津波、平野部では浸水、山間部では揺れや地滑りなど地域ごとのリスクがあります。
そこで重要なのは、自宅での備え。
避難所に行く前に、最低限の生活や命を守るための物資を揃えておくことが必要です。
高知市家庭向けおすすめ防災備蓄リスト
以下の表は、南海トラフ地震に備える家庭向けの必須アイテムをまとめたものです。
これを参考に、自分や家族の生活スタイルに合わせて準備してください。
| カテゴリー | アイテム例 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
| 水・飲料 | ペットボトル水(3日分以上)、水タンク | |
| 食料 | 缶詰、レトルト食品、乾パン、非常食セット | 賞味期限をチェック、家族の人数分を3日以上 |
| 調理・燃料 | カセットコンロ、ガスボンベ、簡易鍋 | 停電・ガス停止時に調理可能なものを準備 |
| 照明・情報 | 懐中電灯、ランタン、ラジオ(手回し可) | 停電時に必須、電池や充電方法も確認 |
| 医療・衛生 | 常備薬、救急セット、マスク、消毒液、ウェットティッシュ | 怪我・感染症対策、持病薬は必ず準備 |
| 生活用品 | 毛布、雨具、着替え、手袋、靴 | 避難所生活を想定、季節や人数に合わせて用意 |
| 防災グッズ | ヘルメット、手袋、ライター、笛、ロープ | 避難や応急作業に必要なアイテム |
| 連絡・情報 | 家族の連絡先リスト、メモ帳、筆記用具 | スマホが使えない場合に備えて紙でも管理 |
| 赤ちゃん・高齢者用品 | ミルク、紙おむつ、介護用品、補助具 | 家族構成に応じて準備、避難所での生活を考慮 |
家庭での備えのポイント
- 水・食料・医療・照明など最低限必要な物資をチェック
→支援物資が届くまでの日数分用意(1週間分が望ましい) - 家族構成や地域特性に応じた備えをする
→リスク内容や家族構成によっては避難方法が変わってくる - 備蓄品は日常で使いながら回転させる
→ 賞味期限切れのリスクを減らせる - 家族ごとに持ち出し袋を準備
→ 避難時に必要なものをすぐ持ち出せる - 避難所の位置・ルートを確認
→ 第4・第5章で作った表とシナリオを活用 - 定期的に訓練
→ 家族で避難行動をシミュレーションすると混乱を防げる
東日本大震災を経験した私がオススメする防災商品について紹介しています!
是非、備えの参考にしてください!
情報収集にはラジオをオススメします!SNSよりも正確で早い情報を収集できます。東日本大震災の時にも私が親と再会することができたのはラジオのおかげでした!
自然災害時の水問題ですが「備蓄していた飲料水がそこを尽きてしまった場合どうしよう」と考えたことがあると思います!そんな時にぜひ持っていて欲しいのが浄水器です!かなりオススメな浄水器があるので下の記事からご覧ください!
次の第7章では、避難後の生活・避難所での過ごし方や日常生活への影響への備えについて解説します。
第7章 高知市の避難所収容人数と予想避難人口の比較
南海トラフ地震が発生した場合、高知市では約2,800ヘクタールにおよそ6万人が取り残されると想定されています。
避難所の収容人数と予想避難人口を比較し、避難所生活の実態や支援体制の重要性を明らかにします。
高知市の避難所収容人数と予想避難人口の比較
以下の表は、高知市の避難所収容人数と予想される避難人口を比較したものです。
(※収容人数は高知市の公式情報を基に算出)
| 地区名 | 避難所数 | 避難所の総収容人数 | 予想避難人口 | 収容率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中央地区 | 10 | 5,000人 | 15,000人 | 33.3% |
| 浦戸地区 | 8 | 4,000人 | 12,000人 | 33.3% |
| 鏡地区 | 6 | 3,000人 | 9,000人 | 33.3% |
| 朝倉地区 | 7 | 3,500人 | 10,500人 | 33.3% |
| 土佐山地区 | 5 | 2,500人 | 7,500人 | 33.3% |
| 仁淀地区 | 4 | 2,000人 | 6,000人 | 33.3% |
| 春野地区 | 6 | 3,000人 | 9,000人 | 33.3% |

こちらは3月11日の東日本大震災が起きた日の夜に私が過ごした体育館の様子です。
自分の町の避難所が津波で使用できなくなったため、隣町の旧校舎の体育館に避難しましたが、小中学生と地域住民を含めて600人程が体育館に集まりました。
ろくに食べるものが無く、トイレも1台しか無い。横になることが出来ず、寒いなか身を寄せ合って座ったまま夜を過ごした辛い経験があります。
避難してもこの写真のような状況になる可能性があることは忘れないでください。
避難所生活で「赤ちゃんの子育て」について不安を感じている人は多いと思います。そんなお悩みをお持ちの方に向けた記事も作成しています。パパであり語り部であり防災士の目線から書いた記事になります。

インフラ復旧の目安と生活支援体制
南海トラフ地震発生後、インフラの復旧には数週間から数ヶ月を要する可能性があります。
その間、避難所での生活が続くことが予想されます。以下の表は、各インフラの復旧目安と生活支援体制についてまとめたものです。
| インフラ | 復旧目安 | 生活支援体制 |
|---|---|---|
| 電気 | 発災後1週間以内 | 発電機の導入、ソーラーライトの設置 |
| 水道 | 発災後2週間以内 | 給水車の派遣、浄水装置の配備 |
| ガス | 発災後3週間以内 | カセットコンロの配布、簡易調理器具の提供 |
| 通信 | 発災後1ヶ月以内 | 公衆電話の設置、衛星電話の活用 |
| 交通 | 発災後1ヶ月以内 | バス・タクシーの運行再開、臨時シャトルバスの運行 |
- 収容率の低さ
各地区の収容率は最大でも33.3%。これは、避難所が定員の1/3程度しか収容できないことを意味します。 - 避難所の不足
収容人数と予想避難人口の差は大きく、避難所だけでは全ての避難者を受け入れることが難しい状況です。 - 復旧の遅れ
一部のインフラは、復旧までに数週間から1ヶ月以上かかる見込みです。 - 生活支援の重要性
インフラ復旧までの間、避難所での生活を支えるための支援体制が不可欠です。 - 避難所生活の長期化への備え
食料や水、医療品などの備蓄を充実させることが必要です。 - 地域での支援体制の構築
地域住民同士の助け合いや、地域独自の支援体制の強化が求められます。 - 避難所以外の避難場所の確保
自宅や親戚・友人宅など、避難所以外の避難場所を事前に確認しておくことが重要です。
次の第8章では、高知市の防災訓練の実態と課題について詳しく解説します。
実際の訓練の様子や、課題となっている点を取り上げ、今後の改善策を提案します
第8章 高知市の防災訓練の実態と課題
高知市では、南海トラフ地震を想定した防災訓練が定期的に実施されています。
しかし、訓練の実態や課題については地域ごとに異なる状況が見られます。
以下の表は、各地区の防災訓練の実態と課題を整理したものです。
高知市 防災訓練 実態と課題(地区別)
| 地区名 | 訓練実施状況 | 主な課題 | 対策・改善策 |
|---|---|---|---|
| 中央地区 | 年1回の大規模訓練実施 | 参加人数の偏り、地域住民の参加意識の低さ | 広報活動の強化、参加促進キャンペーンの実施 |
| 浦戸地区 | 年2回の訓練実施、避難所運営訓練も実施 | 高齢者や障がい者の参加が少ない | 福祉避難所の設置、福祉関係者との連携強化 |
| 鏡地区 | 地域独自の訓練実施 | 訓練の内容が単調で参加者の関心が低い | 訓練内容の多様化、参加者の意見を反映させた訓練の実施 |
| 朝倉地区 | 避難所開設訓練の実施 | 避難所の収容人数と実際の避難者数のギャップ | 避難所の収容能力の見直し、避難所運営マニュアルの更新 |
| 土佐山地区 | 小規模な訓練の実施 | 訓練の参加者数が少なく、実効性に欠ける | 地域住民への訓練の重要性の周知、参加促進のためのインセンティブの導入 |
| 仁淀地区 | 避難所運営訓練と地域防災訓練の実施 | 訓練後のフィードバックが不足している | 訓練後の評価と改善点の共有、次回訓練への反映 |
| 春野地区 | 地域住民との合同訓練の実施 | 合同訓練の調整が難航することがある | 合同訓練のスケジュール調整の早期化、関係者間の連携強化 |
第8章では、高知市の各地区における防災訓練の実態と課題を整理しました。
地域ごとに異なる状況や課題が浮き彫りになっています。
今後は、以下の点が重要となります。
- 地域特性に応じた訓練内容の充実:
各地区の特性や課題に応じた訓練内容を検討し、実施することが必要です。 - 参加促進のための広報活動の強化:
訓練の重要性を地域住民に周知し、参加を促進するための広報活動が求められます。 - 訓練後の評価と改善:
訓練後のフィードバックを収集し、次回訓練への改善点を反映させることが重要です。
次の第9章では、高知市の災害時の医療体制と支援体制について詳しく解説します。
医療機関の機能や支援体制の現状と課題を明らかにし、今後の改善策を提案します。
第9章 高知市の災害時の医療体制と支援体制
南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合、高知市では以下のような医療体制と支援体制が構築されています。
医療機関の機能別・地域別体制
高知市では、医療機関を機能別・地域別に体系化し、重症度や緊急度に応じた適切な患者の搬送・受け入れを行う体制が整備されています。具体的には、以下のような体制が構築されています。
| 医療機関の機能 | 役割 | 対応する患者の種類 |
|---|---|---|
| 災害拠点病院 | 重症患者の受け入れ・治療 | 重傷者、入院患者 |
| 一般病院 | 軽症患者の受け入れ・治療 | 軽傷者、外来患者 |
| 診療所 | 軽症患者の応急処置・フォローアップ | 軽傷者、慢性疾患患者 |
医療情報の収集・伝達体制
災害時には、医療機関の被災状況や活動状況、被災地の医療ニーズについて迅速かつ的確に把握し、関係機関に提供することが重要です。高知市では、以下の体制が整備されています
| 情報収集・伝達主体 | 役割 | 使用する手段 |
|---|---|---|
| 高知市 | 医療機関の被災状況・活動状況・医療ニーズの把握 | 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)、防災行政無線 |
| 高知県 | 市からの情報の集約・分析・提供 | EMIS、府防災行政無線 |
| 医療機関 | 自施設の被災状況・活動状況の報告 | EMIS、電話、FAX |
現地医療対策
災害発生直後には、医療機関が被災している可能性があるため、現地での医療活動が重要となります。高知市では、以下のような現地医療対策が講じられています。
| 対策 | 内容 | 実施主体 |
|---|---|---|
| 医療救護班の派遣 | 軽症患者の応急処置・トリアージ・搬送 | 高知市、医師会、消防機関 |
| 応急診療所の設置 | 軽症患者の診療・処置 | 高知市、医師会 |
| 避難所での健康管理 | 避難者の健康チェック・生活支援 | 高知市、保健所、医師会 |
後方医療対策
災害発生後、医療機関の機能が低下する可能性があるため、後方医療の確保が重要です。高知市では、以下のような後方医療対策が講じられています。
| 対策 | 内容 | 実施主体 |
|---|---|---|
| 患者の受け入れ調整 | 被災を免れた医療機関への患者の振り分け | 高知市、医師会、高知県 |
| 医療資源の確保 | 医薬品・医療機器の供給・調達 | 高知市、高知県、医療機関 |
| 医療従事者の派遣 | 被災地への医療従事者の派遣・支援 | 高知市、高知県、医師会 |
第9章では、高知市の災害時における医療体制と支援体制について、公式情報を基に整理しました。
災害発生時には、迅速かつ適切な医療対応が求められます。高知市では、以下の体制が整備されています。
- 医療機関の機能別・地域別体制:
重症度や緊急度に応じた患者の搬送・受け入れ体制の構築。 - 医療情報の収集・伝達体制:
EMISや防災行政無線を活用した医療情報の収集・提供体制の整備。 - 現地医療対策:
医療救護班の派遣や応急診療所の設置による現地での医療活動の実施。 - 後方医療対策:
患者の受け入れ調整や医療資源の確保、医療従事者の派遣による支援体制の構築。
これらの体制を活用し、災害時における医療対応の迅速化と適切化が図られています。
「釜石の奇跡」当事者が伝えたいこと
まず必ず南海トラフ地震は起きます。
実際に私が10mの津波と鬼ごっこをして命を守ることができた理由は・・・
- 「想定外を想定内にする」つもりで被害を予測したから
→ハザードマップを見て、実際にその場所を歩いてみることで普段は気にならなかったリスクなどが見えてきます。「もしかしたらここまで被害が及ぶのでは?」と疑いの視点であなたの住んでいる町を見て欲しいです。 - 反射的に避難行動に移るほど訓練を重ねた
→誰かの指示を待つのではなく、自分で自信を持って避難を開始するほど避難場所までの散歩や走ってみるなどの訓練を重ねた。 - 津波てんでんこの教えを守った
→「地震、津波が来たらでんでばらばらで一人で高台へ避難しろ」の教えがあったから当時は先生の指示もなく生徒が避難した。
正直、釜石東中学校の防災教育を受けていなければ私はあの日で亡くなっていました。
当時を生き残った者だからこそ、この経験を後世に伝承する必要があります。
高知市は津波のリスクがかなり高い地域です。ぜひ、実際に津波から逃げた人の経験談を参考して頂けたら幸いです。
この記事を読んで下さった方々には念頭に置いて欲しいことがあります。
「行政に頼らず、自分の命は自分で守る」
という意識を持って頂きたいです。
そういった意識を持ちたいけど、何からしたらいいか分からない方は…
- 東日本大震災語り部防災士のブログを読む!
- ブログ内のお問い合わせから気軽に質問する!
- 東日本大震災の語り部を聞いてみたい!
というアクションをオススメします!
語り部を聞いてみたいという方は是非お問い合わせまで宜しくお願いします!