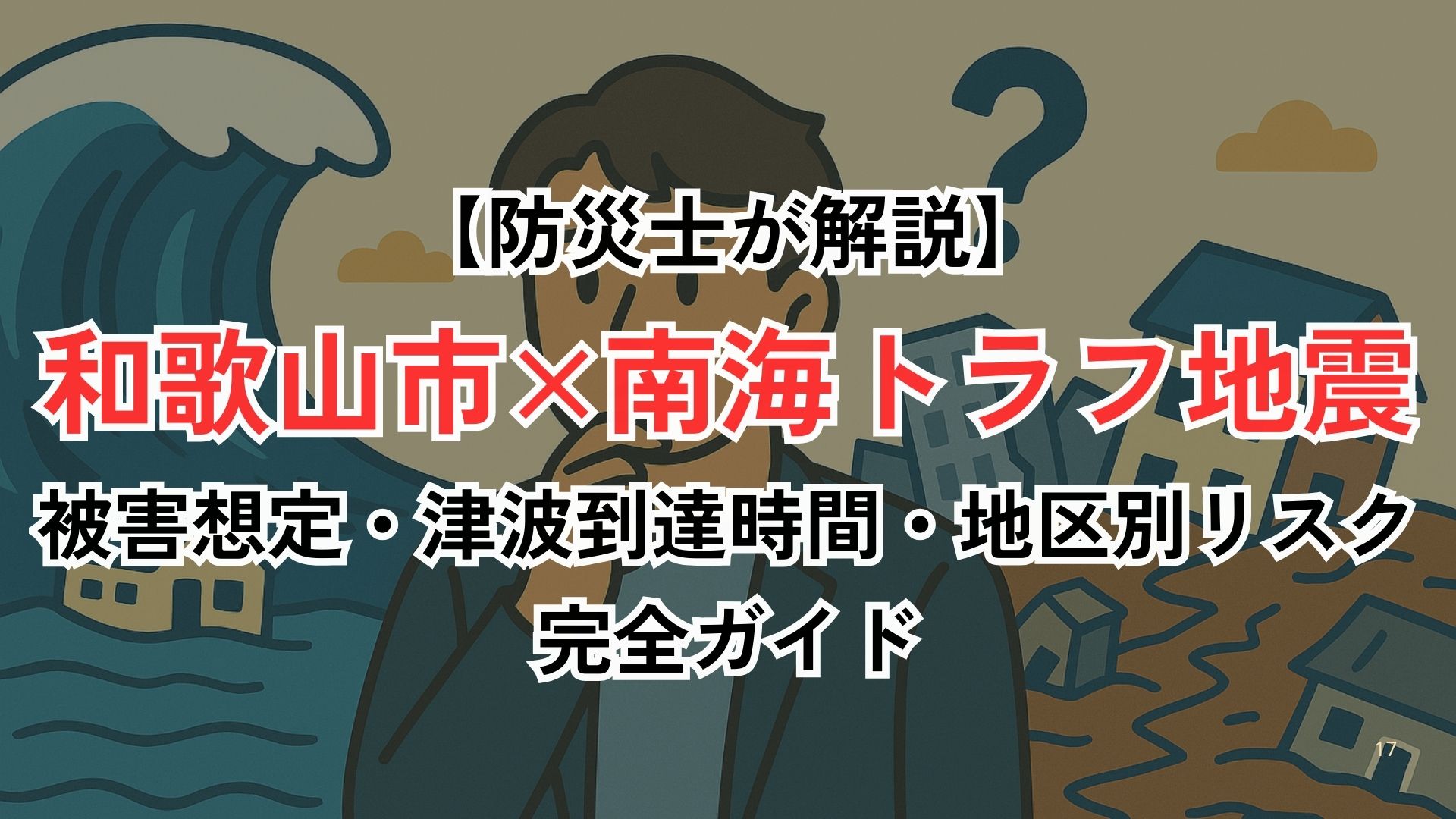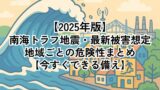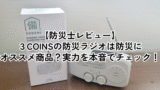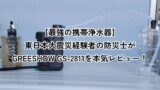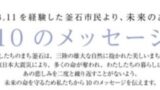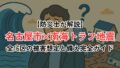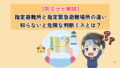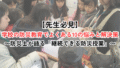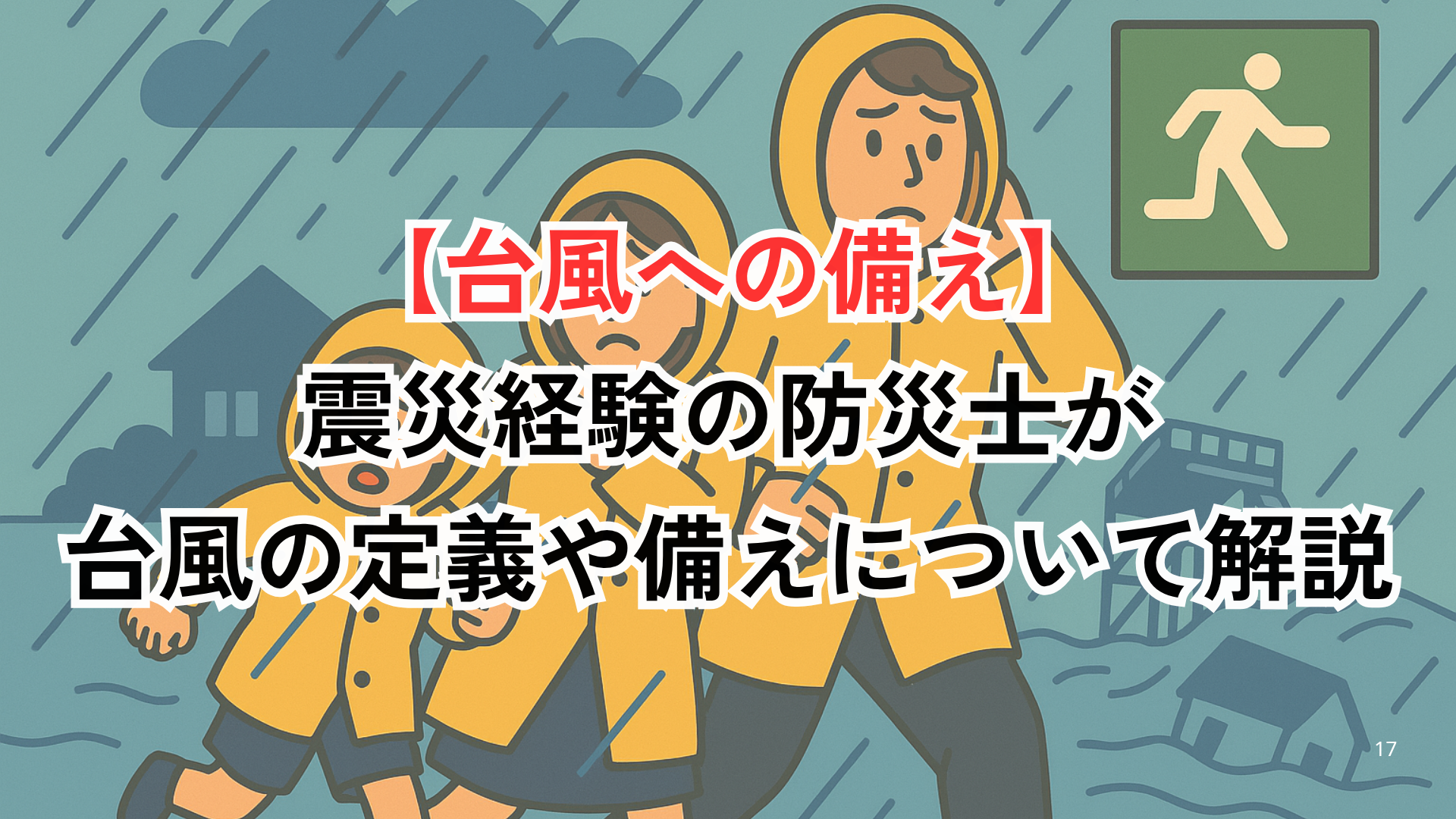第1章 和歌山市を襲う南海トラフ地震とは?
こんにちは、防災士の紺野堅太です。
今回は、南海トラフ巨大地震が和歌山県和歌山市にどんな影響を及ぼすか、具体的なデータとともに東日本大震災を経験した語り部防災士の私の体験談と照らし合わせた「命を守る為の備え」をお届けします。
テレビやネットで「南海トラフがいつ来てもおかしくない」と言われても、正直ピンとこない方も多いと思います。
しかし、和歌山市は太平洋に面しており、津波・揺れ・液状化と、複数の危険が同時に押し寄せる地域です。
まずは、南海トラフ地震の概要と、和歌山市で想定されている被害の全体像を確認しておきましょう。
◆南海トラフ巨大地震ってどんな地震?
南海トラフ地震とは、静岡沖から九州沖までの「南海トラフ」と呼ばれる海底の溝で起こる巨大地震のことです。
過去には100~150年周期で発生しており、前回の「昭和南海地震」(1946年)からすでに約80年が経過しています。
想定される地震の規模は、マグニチュード9.1。
揺れの強さや津波の規模は、東日本大震災と同等、もしくはそれ以上になるとされ、最大で32万人が亡くなるという国の被害想定も出ています。
◆和歌山市に襲いかかる主なリスク
和歌山市に関して言えば、国や和歌山県が発表している想定では、次のような被害が懸念されています。
| リスクの種類 | 想定される影響 |
|---|---|
| 揺れ(震度) | 最大震度6強(場所によっては震度7に迫る) |
| 津波 | 高さ9〜12mの津波が10分~30分で到達 |
| 液状化 | 河川沿いや埋立地(和歌川沿い、雑賀崎など)に多発の可能性 |
| 火災 | 木造密集地(城北・本町・吹上エリアなど)で延焼拡大の恐れ |
とくに津波については、発災から非常に短時間で襲ってくる可能性が高く、沿岸部では「5分以内の避難行動」が生死を分けると言われています。
◆一目で分かる!津波到達時間と最大高さ一覧
以下に、和歌山市内の主要地域ごとの「津波の最大高さ」と「最短到達時間」を表でまとめました。
※出典:和歌山県津波浸水想定(2023年3月改訂)
| 地域名 | 最大津波高(m) | 最短到達時間(分) |
|---|---|---|
| 雑賀崎(さいがさき) | 約12.1m | 約6分 |
| 和歌浦(わかのうら) | 約11.3m | 約8分 |
| 紀三井寺(きみいでら) | 約10.8m | 約9分 |
| 西浜・毛見エリア | 約10.5m | 約10分 |
| 市駅〜本町エリア | 約3.2m | 約18分 |
| 六十谷(むそた)・紀伊中ノ島 | 約1.5m | 約25分 |
| 紀ノ川河口周辺 | 約5.4m | 約12分 |
🔸注目ポイント
・市街地中心部でも最大3〜5mの津波が押し寄せる見込み
・特に雑賀崎〜和歌浦沿岸は津波が最も早く、10分以内で到達
・「避難は揺れを感じたらすぐ」が大原則
◆和歌山市で過去に起こった津波被害
和歌山市は過去にも津波被害を経験しています。
たとえば1946年の「昭和南海地震」では、現在の和歌浦エリアに最大4〜5mの津波が押し寄せ、多くの家屋が流失・浸水しました。
現代の建物や港湾施設は強化されていますが、住宅密集地や高齢化が進む地域では避難に時間がかかるため、過去よりも被害が拡大する可能性があります。
第2章|和歌山市の地区別リスク分析|津波・液状化・火災
南海トラフ地震の脅威は「和歌山市全域」に及びますが、地形・海抜・地盤の違いにより、被害のリスクや特性は地区によって大きく異なります。この章では、防災士の視点で「津波」「液状化」「火災」の主な3つのリスクを、和歌山市内の主な地区ごとに表使って見える化していきます。
◆和歌山市の地区別リスク一覧表(津波・液状化・火災)
| 地区名 | 津波リスク(最大高・到達時間) | 液状化リスク | 火災リスク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 雑賀崎・田野・新和歌浦 | 最大8.5m/約10分〜20分 | 低〜中 | 低 | 海に近く津波リスクが極めて高い |
| 和歌浦・和歌浦南・和歌浦中 | 最大7.6m/約15分 | 中 | 低 | 津波避難路・高台へのアクセスが鍵 |
| 和歌山港周辺(西浜・西浜新町) | 最大9.1m/約5分〜10分 | 高 | 中 | 港湾部・工業地帯、液状化+津波で複合被害 |
| 湊・湊御殿・築港 | 最大8.8m/約7分 | 高 | 高 | 石油施設や工場密集地、津波+火災の複合懸念 |
| 中之島・太田・友田町 | 最大4.3m/約20〜30分 | 中 | 高 | 海からやや距離あり、内陸火災に注意 |
| 北島・延時・狐島 | 最大5.5m/約15〜25分 | 中 | 中 | 和歌川・内川が近く、津波+液状化リスクあり |
| 市駅周辺(本町・駿河町) | 最大3.8m/約25〜30分 | 低〜中 | 高 | 商業地密集、火災発生時の延焼リスク高 |
| 紀三井寺・小雑賀 | 最大6.7m/約10〜15分 | 中 | 低 | 紀三井寺駅周辺も津波リスク中程度 |
| 岡山・岩橋・和田 | 最大2.5m/約30〜40分 | 中 | 中 | 内陸側で直接津波の影響は小さいが揺れ対策必要 |
| 海南市境(布施屋・松江) | 最大1.0m未満/約40分〜 | 中 | 低 | 津波被害は少ないが液状化の可能性あり |
解説①|津波リスクは「港湾部」と「海岸近く」が最も深刻
和歌山市の中でも、「和歌山港」や「雑賀崎」「和歌浦」などの臨海エリアは、津波の到達時間が非常に短く、最速で5分以内に8〜9mの津波が押し寄せると想定されています。これは地震発生からわずかな時間しかないことを意味しており、揺れを感じたら即避難が命を守る最優先行動です。
また、紀三井寺〜西浜エリアの一部は、海抜が低く、かつ津波の引き潮による孤立リスクも高いため、日頃からの避難経路・高台確認が重要です。
解説②|液状化は「埋立地」や「川沿い」で注意
液状化リスクが高いのは以下のような地盤の場所です:
- 和歌山港の周辺(西浜・築港・湊):埋立地で地盤が弱く、液状化によって建物や道路の沈下が起きやすい。
- 内川沿いの北島・延時・狐島エリア:川の近くで地下水位が高く、地震による地盤の変形に注意。
- 太田・中之島付近:比較的地盤が軟弱な箇所が多く、避難の際のインフラ影響も心配される。
液状化は、津波や火災とは違い即時の生命の危険は少ないですが、避難路の通行不能や断水・電力喪失の要因となるため、間接的に命に関わる問題として軽視できません。
| 地区名 | 埋立地割合 | 液状化リスク | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 西浜・築港 | 約80% | 非常に高い | 港湾施設集中、埋立造成地 |
| 和歌浦港 | 約60% | 高い | 観光港・漁港が混在 |
| 紀ノ川河口部 | 約50% | 高い | 河川氾濫と複合被害の懸念 |
| 湊本町周辺 | 約40% | 高い | 商業地と住宅地混在 |
| 松江・中松江 | 約30% | 中 | 旧河川敷が多く軟弱地盤 |
| 東部丘陵地(楠見・園部) | 0% | 低い | 固い地盤で液状化可能性小 |
解説③|火災リスクは「市街地・工業地帯」で高い
大地震の際、火災リスクが高まるのは以下の要因によります:
- ガス漏れ・電気ショートによる出火
- 老朽木造住宅密集地の延焼
- 工場・石油施設からの火災拡大
そのため、
- 湊・築港・湊御殿などの工業地帯
- 本町や中之島・太田などの住宅密集地・商業地
では、火災が発生した場合の被害の広がりが懸念されます。
特に、旧市街地に多い狭い道路・木造建築の密集エリアでは、消火活動が困難になり、“地震火災”による大規模延焼の恐れも指摘されています。
◆地域別リスクを知ることが“命を守る準備”になる
災害時に「自分がどの地区にいるか」によって、取るべき行動や備えるべき対策は大きく変わります。
- 津波リスクが高い地区:高台・ビル避難の確認と素早い行動力
- 液状化リスクが高い地区:飲料水やトイレ対策などインフラ喪失の備え
- 火災リスクが高い地区:防火グッズ、避難ルートの確保と周囲との連携
このように「地域ごとのリスクの違い」を知っておくことで、より現実的で効果的な防災行動につなげることができます。
そして地域ごとのリスクを理解するために用いるのがハザードマップです。
ハザードマップを確認することで災害リスクの内容と範囲を確認することができます。
和歌山市で出しているハザードマップや国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」などもあります。
こちらの記事ではハザードマップポータルサイトの使い方をまとめています。是非ご覧ください。
第3章|和歌山市の避難所と避難ルート
南海トラフ地震の発生時、和歌山市における命を守る行動の最優先は「揺れから身を守り、すぐに安全な場所へ避難すること」です。特に津波警報が発表された場合、臨海部は発生から5〜10分で津波到達という短さのため、地震発生直後の判断と行動が生死を分けます。
本章では、「避難所の位置・設備」と「避難ルート」を、津波・液状化・火災リスクを踏まえて詳しく解説します。
◆和歌山市の避難所の全体傾向
和歌山市は市内全域に約140カ所の指定避難所を配置しています。内訳としては、
- 臨海部:津波避難ビルや学校・公共施設が主体
- 市街地・内陸部:体育館併設の学校、公園隣接施設など
- 山間部:公民館や集会所を活用
また、避難所のうち「津波避難ビル」に指定されている施設は臨海部に集中しており、高さや構造、立地の安全性から選ばれています。
◆津波避難ビルと避難所の主な一覧(地区別)
主な各地区津波避難ビル一覧
| 地区名 | 津波避難ビル名・施設名 | 想定収容人数 | 備考・特徴 |
|---|---|---|---|
| 雄湊地区 | 県営住宅 雄湊団地 | 約200人 | 一階以上の共用部が避難対象(津波避難施設指定) |
| 西浜/築港 | 県営住宅 西浜団地 | ―(公表なし) | 場所と構造より地区最大規模の高層施設と推定 |
| 太田地区 | 県営住宅 和歌山東団地 | 約660人 | 津波避難ビル指定、エリア最大収容数 |
| 毛見/紀三井寺 | ファシナシオン毛見II | 約171人 | 津波避難ビル指定、団地型集合住宅 |
| その他エリア(和歌浦/紀三井寺以外) | — | — | 指定津波避難ビルなし、学校等避難所に準拠 |
主な各地区避難所の一覧
| 地区名 | 主な避難所名 | 設備 | 特徴・備考 |
|---|---|---|---|
| 西浜・築港 | 西浜中学校 | 非常電源・備蓄倉庫・井戸 | 津波避難ビル併設、港湾から近く高台方向へも避難可 |
| 湊・湊御殿 | 湊小学校 | 太陽光発電・受水槽 | 津波避難ビル指定、工業地帯従業員の避難想定 |
| 和歌浦 | 和歌浦小学校 | 非常電源・炊き出し器具 | 高台へ直接避難できる立地 |
| 雑賀崎 | 雑賀小学校 | 簡易トイレ・備蓄水 | 高台に立地、津波避難優良地 |
| 中之島 | 伏虎義務教育学校 | 非常電源・多目的トイレ | 内陸側の広域避難所、帰宅困難者受け入れ可 |
| 紀三井寺 | 紀三井寺小学校 | 非常電源・井戸 | 津波避難指定、海からやや距離あり |
| 北島 | 北島小学校 | 太陽光発電・防災倉庫 | 津波+液状化複合リスク対応 |
| 本町・市駅周辺 | 伏虎義務教育学校北分校 | 多目的トイレ・備蓄倉庫 | 商業地帰宅困難者の一次避難地 |
津波避難ビルや避難場所を把握することで逃げるべき安全な場所を把握することができます。
まずは「安全な場所」=「避難のゴール」を把握しておかないと避難時の初動対応が遅れます。
避難場所もハザードマップで確認することができます。また、避難場所と避難所を勘違いされる方が多いです。
こちらの記事を読んで事前に違いを把握しておきましょう!
◆津波避難ビルの特徴と選定理由
津波避難ビルの指定は、次の基準に基づいて行われています。
- 鉄筋コンクリート造3階以上で耐震性が高い
- 海抜・標高が高く、津波浸水想定区域外または被害軽減可能な位置
- 避難収容人数が多く、周囲からのアクセスが容易
- 夜間や休日でも立ち入り可能
特に和歌山港周辺(西浜・築港・湊)は、港湾・工業施設従業員や漁業関係者の緊急避難を想定し、複数の津波避難ビルが密集して配置されています。
◆主な避難ルート(支援・交通網と連動)
地震発生後、支援物資や救援部隊は和歌山市の以下のルートを使って輸送されます。
- 国道42号:田辺〜海南〜和歌山市中心部の生命線
- 国道26号:大阪方面からの救援ルート
- 阪和自動車道:高速道路経由の緊急輸送路
- 南海電鉄・JR紀勢本線:人員輸送および帰宅困難者対応
- 和歌山港フェリー:四国方面からの物資輸送(徳島港経由)
臨海部の一部は液状化や津波によって道路が寸断される恐れがあり、内陸部への高台ルート確保が重要です。
◆災害時の避難のポイント
- 揺れたらすぐ身の安全を確保してから避難開始
まずは机の下に潜って、頭を守るなどをして身の安全を確保します。その後に避難開始です。臨海部は地震から数分で津波到達のため、事前に避難場所を把握しておきましょう。 - 車両避難を控える
車は渋滞・津波巻き込みリスク大。避難が遅れる可能性が高いので基本は走って避難をしましょう。しかし、怪我人やパニックにて過呼吸になる人もいます。そういった場合は車両で避難できる場所までは避難してもいいです。 - 避難所までの複数ルートを事前確認
1本のルートが使えない場合に備え、別ルートも把握しておく。 - 夜間・雨天の避難も想定
懐中電灯や防水装備は常に避難袋へ。
◆避難所・避難ルートの見える化表
| エリア | 津波到達時間 | 推奨避難先 | 主避難ルート | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 西浜・築港 | 約5分 | 西浜中学校 | 港大通り→高台方向 | 液状化で道路冠水の恐れ |
| 湊・湊御殿 | 約7分 | 湊小学校 | 築港通り→北島高台 | 工場火災の煙を避ける |
| 和歌浦 | 約15分 | 和歌浦小学校 | 海岸通り→高台公園 | 観光客の混雑注意 |
| 紀三井寺 | 約10分 | 紀三井寺小学校 | 駅南通り→高台 | 踏切渋滞に注意 |
| 北島 | 約15分 | 北島小学校 | 北島通り→高台 | 液状化で歩行困難箇所有 |
| 中之島 | 約20分 | 伏虎学校 | 市街地大通り→避難所 | 商業地火災に注意 |
和歌山市の避難所と避難ルートは、津波・液状化・火災の複合リスクを考慮して配置されています。特に臨海部では、「身の安全を確保後に即避難」が最も重要です。
- 臨海部は津波避難ビルを最優先
- 液状化エリアは避難ルートの事前確認
- 火災高リスク地帯は広い道路・高台経由
次章では、地震後の生活シナリオと物資供給までの時間を詳しく分析し、支援が届くまでの現実的な日数と備えについて解説します。
第4章|地震後の生活シナリオと物資供給までの現実
南海トラフ地震が和歌山市を襲った場合、揺れによる建物被害や津波浸水だけでなく、その後の日常生活が長期にわたり制限される現実が待っています。避難所での生活、物資の不足、インフラの復旧の遅れは、多くの市民にとって経験したことのないほど厳しい状況になるでしょう。
この章では、災害発生直後から物資供給が安定するまでの時間の流れを追いながら、実際に想定される生活シナリオを解説します。
◆発災直後(0〜24時間)
津波警報と避難
- 臨海部は地震発生後わずか5〜10分で津波到達の恐れ
- 高台や津波避難ビルへの即時避難が命を守る鍵
- 夜間・早朝の発生時は暗闇・寒さ・混乱が避けられない
混乱と情報不足
- 停電によりテレビ・インターネットの情報取得が困難
- スマートフォンは基地局や通信網被害で数時間以内に通信不能
- 防災行政無線やコミュニティFMが生命線になる
◆発災後1〜3日目
避難所生活の開始
- 市内約140カ所の避難所に避難者が殺到
- 体育館や公民館は過密状態になり、プライバシーや衛生面の課題が顕在化
- 高齢者や乳幼児、持病のある人は健康被害のリスク増大
水・食料の不足
- 発災直後の3日間は自助が基本とされ、行政からの十分な物資供給は困難
- 市内のコンビニ・スーパーは在庫が数時間〜半日で枯渇
- 給水車は道路寸断や渋滞で到着が遅れる
◆発災後4〜7日目
物資供給の本格化
- 陸路:国道42号・26号、阪和自動車道を経由し大阪・奈良方面から救援物資が到着
- 海路:和歌山港経由で四国(徳島)からも物資搬入
- しかし港湾施設や道路の被害次第で大幅な遅延の可能性
支援物資の優先順位
- 水(飲料用)
- 食料(パン・缶詰・レトルト)
- 救急・医薬品
- 毛布・防寒具
- 携帯トイレ
避難者の多い臨海部や津波被災地が優先されるため、内陸部では物資到着がさらに遅れる場合あり。
◆発災後2週間〜1カ月
インフラ復旧の遅れ
- 電気:数日〜1週間程度で部分復旧するが、浸水地域は数週間かかる可能性
- 水道:断水は最大1カ月以上継続するケースあり(過去震災の事例より)
- ガス:地中管の安全確認に時間を要し、復旧まで数週間〜数カ月
避難所生活の長期化
- 津波被害地域では住宅再建まで避難生活が長期化
- 仮設住宅建設まで数カ月かかるため、避難所や親戚宅での生活が続く(私が東日本大震災を経験した時は5月下旬に仮設住宅へ入居しました)
| インフラ | 復旧目安(市街地) | 復旧目安(沿岸・被害甚大地域) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電力 | 3日〜1週間 | 2〜3週間 | 倒壊電柱・津波浸水による配電盤損傷 |
| 上水道 | 1〜2週間 | 1〜2か月 | 配水管破損、浄水場浸水 |
| 下水道 | 2週間〜1か月 | 2か月以上 | 管路のずれ・マンホール浮上 |
| ガス | 2〜3週間 | 1〜2か月 | 埋設管破断・漏洩点検 |
| 通信(携帯) | 数日〜1週間 | 1〜2週間 | 基地局損壊・停電 |
| インターネット | 1週間 | 2〜3週間 | 光ケーブル断線 |
◆支援物資の到着見込みとルート
| 支援種別 | 想定到着日数 | 主な輸送ルート | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水(飲料用) | 1〜3日 | 国道42号・26号/和歌山港 | 避難所最優先で配送 |
| 食料 | 2〜5日 | 同上 | パン・米飯・レトルト中心 |
| 医薬品 | 2〜5日 | 大阪医療拠点から搬送 | 要冷蔵薬品は遅延リスクあり |
| 毛布・防寒具 | 3〜7日 | 阪和道〜市内各避難所 | 冬季は特に優先度高 |
| 携帯トイレ | 3〜7日 | 大阪府・奈良県から供給 | 公共トイレ復旧まで必須 |
◆災害時の生活維持のポイント
- 3日間は自力で生き延びる備え
- 水3L×人数分/1日
- 主食(米・パン・麺類)3日分
- カセットコンロ・ボンベ
- お菓子やゼリー等
- 冷蔵庫の中身(肉や魚などはすぐに悪くなるため、火を使える状態であれば先に食べた方がいい)
- 衛生管理の徹底
- 携帯トイレ・ウェットティッシュ必須
- マスクで感染症対策
- 情報収集の多様化
- 防災ラジオ・ワイドFM
- 近隣避難所との連携
和歌山市における南海トラフ地震後の生活は、水・食料・情報不足が3つの大きな壁になります。特に津波被災地では道路や港湾の被害で物資が遅れやすく、最初の3日間を生き延びられる備蓄が命綱です。
情報収集にはラジオをオススメします!SNSよりも正確で早い情報を収集できます。東日本大震災の時にも私が親と再会することができたのはラジオのおかげでした!
自然災害時の水問題ですが「備蓄していた飲料水がそこを尽きてしまった場合どうしよう」と考えたことがあると思います!そんな時にぜひ持っていて欲しいのが浄水器です!かなりオススメな浄水器があるので下の記事からご覧ください!
避難所生活で「赤ちゃんの子育て」について不安を感じている人は多いと思います。そんなお悩みをお持ちの方に向けた記事も作成しています。パパであり語り部であり防災士の目線から書いた記事になります。

第5章|津波避難場所リストと避難ビルの詳細
南海トラフ地震では、和歌山市の沿岸部は地震発生からわずか5〜10分で津波が到達する可能性が高いとされています。特に港湾部・和歌浦地区・紀ノ川河口周辺では、第一波の到達が非常に早く、迷わず高台や津波避難ビルに向かう行動が命を守ります。
ここでは、和歌山市の津波避難場所(高台・避難ビル)と、その設備・立地条件を整理します。
◆和歌山市における津波避難の基本方針
- 沿岸部の住民・滞在者は、揺れを感じたら身の安全を確保して、すぐ避難を開始(津波警報の発令を待たない)
- 高台避難が可能な地域は山側へ移動(紀三井寺・和歌浦周辺)
- 高台がない地域は、近くの津波避難ビル・鉄筋コンクリート造の3階以上の建物へ(土砂崩れが無ければ山の上でも大丈夫です。とにかく高い場所へ避難)
- 夜間や観光客向けに、避難経路の常時確認が必要
◆津波避難場所・避難ビル一覧(主要エリア)
第3章でも津波避難ビルの表をご覧頂きましたが、より詳細のリストがこちらになります。
| 地域 | 津波避難ビル・施設名 | 所在地 | 高さ(階) | 設備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西浜 | 西浜中学校 | 西浜3丁目 | 3階 | 非常用電源・トイレ | 港湾部住民の主要避難所 |
| 西浜 | 西浜消防署 | 西浜2丁目 | 4階 | 無線通信・発電機 | 消防拠点兼用 |
| 築港 | 築港小学校 | 築港3丁目 | 3階 | 給水ポンプ | 浸水エリア中心部に位置 |
| 和歌浦 | 和歌浦小学校 | 和歌浦東3丁目 | 3階 | 非常用電源 | 高台方向避難が難しい場合に有効 |
| 紀三井寺 | 紀三井寺中学校 | 紀三井寺3丁目 | 3階 | トイレ・倉庫 | 高台避難可能だが補助施設 |
| 中之島 | 和歌山県立体育館 | 中之島223 | 4階 | 発電機・飲料水備蓄 | 内陸側の広域避難所 |
| 松江 | 松江小学校 | 松江北1丁目 | 3階 | 太陽光発電・トイレ | 紀ノ川沿い避難拠点 |
| 新南 | 新南公民館 | 新南2丁目 | 3階 | 無線通信 | 地域防災拠点として活用 |
※実際は和歌山市内に100カ所以上の津波避難ビルがあり、その多くは学校、公民館、官公庁施設。
◆地域別 津波避難施設の分布と特徴
(1) 西浜・築港エリア
- 港湾部のため津波到達が最短
- 避難ビルが密集しているが、第一波前に到達するには徒歩5分圏内が目安
- 工場地帯も多く、夜間の人員避難に課題
(2) 和歌浦・紀三井寺エリア
- 高台方向への避難が可能
- 海沿い旅館や観光施設は観光客誘導のマニュアル整備が重要
- 避難ビルは観光客向けにも案内板整備が進む
(3) 松江・紀ノ川河口周辺
- 河川遡上津波の危険あり
- 高台が近くにないため、避難ビル依存度が高い
- 水害と津波の複合災害を想定した避難訓練が必要
◆津波到達時間・高さの目安(和歌山市主要地点)
| 地域 | 津波到達時間 | 最大想定高さ |
|---|---|---|
| 西浜 | 約5分 | 約4〜6m |
| 築港 | 約5分 | 約4〜6m |
| 和歌浦 | 約7分 | 約3〜5m |
| 紀三井寺 | 約8分 | 約2〜4m |
| 松江 | 約6分 | 約4〜5m |
| 中之島 | 約12分 | 約1〜2m |
※到達時間は南海トラフ巨大地震(冬・満潮時)想定。地域によってはさらに早まる可能性あり。
◆津波避難ビルに指定される理由
津波避難ビルの指定条件には以下のような基準があります。
- 鉄筋コンクリート造(RC造)または鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
- 浸水想定を超える高さ(おおむね3階以上)
- 耐震性能が基準を満たしている
- 避難階にトイレや電源など最低限の生活機能がある
- 24時間365日立ち入りが可能、または迅速に開放できる体制
◆観光地特有の課題と対策
和歌浦・紀三井寺・加太など観光客が多い地域では、
- 観光客が避難場所を把握していない
- 言語・案内板不足
- 夜間イベント時の避難誘導が難しい
これらを踏まえ、市は外国語対応の案内板や夜間誘導訓練を強化しています。
◆避難判断を迷わないために
- 避難ビルまでの徒歩ルートを日常から確認
- 高齢者や子ども連れは発災時の補助役を事前に決める
- 家族や職場で「地震後はどこに逃げるか」共通認識を持つ
和歌山市の津波避難ビルは市内各所に分布していますが、本当に使えるのは発災直後に徒歩5分以内で到達できる場所です。南海トラフ地震では、揺れの収まりを待たず即行動に移れるかが生死を分けます。
第6章|主避難所の詳細と運営実績
南海トラフ地震後の避難生活は、避難所の環境・設備・運営力によって生活の質や健康状態が大きく左右されます。
和歌山市では、市内全域に指定避難所(約140カ所)が設置されていますが、その中でも収容人数・設備・運営体制が充実している主避難所は限られています。
ここでは、和歌山市における主避難所の概要、設備状況、訓練実績をまとめ、発災後の避難生活をできるだけ快適かつ安全に過ごすための情報を整理します。
◆主避難所の役割
主避難所は以下のような特徴を持ち、災害時に地域防災拠点の中核を担います。
- 広い体育館や多目的ホールを持ち、大人数を収容可能
- 給水設備や非常用発電機などの生活インフラが整備
- 物資集積・配布の拠点として機能
- 地域防災リーダーや自治会と連携した運営体制を持つ
- 避難所運営訓練の実施頻度が高く、災害対応経験が豊富
◆和歌山市の主避難所一覧
| 避難所名 | 所在地 | 主な設備 | 訓練実績 |
|---|---|---|---|
| 和歌山ビッグホエール | 手平2丁目1-1 | 大型体育館・発電機・備蓄倉庫 | 年1回大規模訓練 |
| 和歌山県立体育館 | 中之島223 | 発電機・受水槽・多目的ホール | 年1回 |
| 西浜中学校 | 西浜3丁目 | 非常用電源・井戸・トイレ | 年2回 |
| 松江小学校 | 松江北1丁目 | 太陽光発電・給水設備 | 年1回 |
| 紀三井寺中学校 | 紀三井寺3丁目 | 倉庫・簡易ベッド | 年1回 |
| 和歌山東公民館 | 友田町4丁目 | 発電機・トイレ | 年1回 |
| 宮前小学校 | 宮前1丁目 | 井戸・トイレ | 年1回 |
| 伏虎義務教育学校 | 七番丁 | 体育館・備蓄倉庫 | 年2回 |
| 有功中学校 | 栄谷 | 発電機・給水設備 | 年1回 |
| 西脇中学校 | 西脇 | 発電機・トイレ | 年1回 |
◆設備の特徴と重要性
(1) 非常用発電機
- 停電時でも照明・通信機器・一部の電化製品を使用可能
- 医療機器(酸素吸入器、簡易心電計)の稼働にも重要
- 定期点検が必要で、稼働確認が不十分な避難所もあるため事前情報が重要
(2) 給水設備・井戸
- 水道断水が長期化した場合に生命線となる
- 深井戸の場合は電動ポンプ稼働に発電機が必要
- 手押しポンプ式井戸を併設している避難所はより安心
(3) トイレ設備
- 洋式トイレ・簡易トイレ・車いす対応トイレなど多様な設備が望ましい
- 仮設トイレの搬入には数日かかる可能性が高く、初期の衛生管理が課題
(4) 太陽光発電+蓄電池
- 長期停電時の補助電源として有効
- 携帯電話充電や照明確保が可能
◆避難所運営訓練の重要性
避難所運営は単に施設を開放するだけではなく、以下の課題に対応する必要があります。
- 避難者の受付・名簿作成
- 食料・水・物資の配給管理
- 高齢者・要配慮者への介護・医療支援
- ごみ処理・衛生管理
- 防犯・プライバシー確保
和歌山市では、年1〜2回の避難所運営訓練を実施している施設が多く、特に「和歌山ビッグホエール」「西浜中学校」「伏虎義務教育学校」などは地域住民を巻き込んだ訓練で評価が高いです。
◆要配慮者への対応
災害時、特に配慮が必要な方々への支援は避難所運営の大きな課題です。
- 高齢者・障害者・乳幼児連れ世帯への優先的な居住スペース確保
- アレルギー対応食の備蓄
- 医療用電源の確保
- 手話通訳や多言語対応スタッフの配置
◆避難所選びのポイント
- 自宅から徒歩・自転車で安全に到達できる距離か
- 避難所の収容人数と実際の混雑状況
- 井戸や発電機など生活維持設備の有無
- 地域防災訓練への参加度合い
- 高齢者や子どもへの配慮体制
和歌山市の主避難所は設備や運営力に差があります。発災時に「どこに逃げれば生活が維持できるのか」を知るためには、事前に近隣の避難所の設備や訓練実績を把握しておくことが極めて重要です。
特に発電機・給水設備・トイレ設備の有無は、長期避難生活の快適性と健康を大きく左右します。
第7章|過去の地震被害と教訓
和歌山市は南海トラフ地震の想定震源域に近く、歴史的にも繰り返し大きな地震と津波に見舞われてきました。
この章では、過去の主要な地震被害の記録と、それらから導き出される防災の教訓を整理します。
◆歴史に残る主要地震と和歌山市の被害
(1) 宝永地震(1707年10月28日)
- 規模:M8.6(南海トラフ巨大地震)
- 津波被害:和歌山市沿岸で推定6〜8mの津波
- 被害概要:
- 市街地の大半が浸水
- 和歌浦周辺で多数の家屋流失
- 船舶・港湾施設の壊滅
- 紀ノ川河口付近で大規模地形変化
- 教訓:津波到達が早く、高台避難の必要性が明確化。港周辺では「津波石」などの災害記録が残された。
(2) 安政南海地震(1854年12月24日)
- 規模:M8.4
- 津波被害:
- 推定5〜7mの津波が来襲
- 西浜・築港エリアで広範囲浸水
- 被害概要:
- 木造住宅の倒壊多数
- 和歌山城下町の一部も浸水
- 多くの漁港集落が壊滅的打撃
- 教訓:沿岸部の集落は津波からの再建を余儀なくされ、津波避難場所や石碑が多数設置された。
(3) 昭和南海地震(1946年12月21日)
- 規模:M8.0
- 津波被害:
- 和歌山市沿岸で津波高3〜4m
- 築港・西浜・和歌浦の漁港施設が大きな被害
- 被害概要:
- 木造家屋倒壊
- 紀ノ川沿岸の液状化被害
- 港湾施設の大規模破損
- 教訓:液状化と津波の複合被害を想定したまちづくりの必要性。
(4) 2004年紀伊半島南東沖地震
- 規模:M7.4
- 津波被害:
- 津波高1m未満
- 沿岸部で軽微な浸水
- 被害概要:
- 港湾部で護岸の一部損傷
- 液状化による局所的地盤沈下
- 教訓:比較的小規模の地震でも液状化が発生することが確認され、インフラの耐震化の重要性が再認識された。
◆過去地震の被害傾向(和歌山市)
| 地震名 | 発生年 | 想定M | 津波高(推定) | 液状化 | 主な被害 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝永地震 | 1707 | 8.6 | 6〜8m | 記録なし | 和歌浦・港湾部壊滅 |
| 安政南海地震 | 1854 | 8.4 | 5〜7m | 記録なし | 城下町・沿岸集落浸水 |
| 昭和南海地震 | 1946 | 8.0 | 3〜4m | 有 | 木造家屋倒壊、港湾被害 |
| 紀伊半島南東沖地震 | 2004 | 7.4 | 1m未満 | 有 | 港湾損傷、地盤沈下 |
◆被害の共通点と教訓
(1) 津波到達の早さ
- 過去の記録では最短5分以内で津波到達の事例あり
- 揺れの収まりを待たず避難開始が命を守る
(2) 港湾・沿岸集落の壊滅的被害
- 西浜・築港・和歌浦が繰り返し被災
- 港湾復旧に数年を要した例もある
(3) 液状化の発生
- 紀ノ川河口や港湾部で頻発
- 地盤改良や耐震補強の重要性
(4) 木造家屋の倒壊
- 古い木造住宅は震度6強クラスで倒壊の危険大
- 耐震改修の促進が必須
◆現代に活かす防災戦略
- 即時避難行動の徹底
- 揺れを感じたら迷わず高台や避難ビルへ
- 港湾・河口部のインフラ強化
- 抑止護岸・耐震岸壁の整備
- 液状化対策
- 埋立地や低地の地盤改良
- 耐震改修の推進
- 特に戦前〜昭和中期建築の木造家屋
- 地域訓練と啓発
- 学校・自治会・観光業界を巻き込む
和歌山市は、宝永地震から昭和南海地震、そして近年の紀伊半島沖地震まで、繰り返し同じ地域が被災するパターンを持っています。
この事実は、南海トラフ地震発生時にも同様の被害が再現される可能性を示しています。
特に港湾部・紀ノ川河口周辺・和歌浦地区は、津波・液状化・地盤沈下が複合する「多重リスク地域」です。これらの地域では、発災直後の即時避難と、事前の住宅耐震化・液状化対策が生死を分ける鍵になります
第8章|ここまでのまとめと経験者からのメッセージ
南海トラフ地震は、30年以内の発生確率が70〜80%とされ、和歌山市にとって避けられない脅威です。
本記事では、全体被害予測から地区別リスク、行政の備え、生活シナリオ、津波避難場所や避難所情報、過去の地震の教訓、液状化マップ、復旧・支援見通しまでを総合的に解説しました。
改めて大事なポイントについてお伝えします。
◆和歌山市は「津波・液状化・揺れ」の三重リスク
- 津波:和歌山市沿岸部では、最短10分以内で高さ10m超の津波が到達する想定
- 液状化:港湾部や河口部の埋立地は非常に高いリスク
- 強い揺れ:震度6強〜7が想定され、木造住宅を中心に倒壊危険
つまり、南海トラフ地震は「地震+津波+液状化」が複合的に発生する可能性が高く、単一の対策だけでは命を守れません。
◆発災直後の72時間が生死を分ける
- 救助活動が本格化するのは発災から3日目以降
- 初動は自己完結型の生活(食料・水・電源・情報源)を確保する必要あり
- 家族間での「発災時の役割分担」を事前に決めておく
例:
- 高台へ避難する役
- 非常持ち出し袋を持ち出す役
- 近所の高齢者や子どもを誘導する役
◆避難行動のゴールデンタイムは「発災直後〜津波到達前」
- 津波は揺れが収まってから数分〜十数分で到達する可能性あり
- 揺れが強かったら迷わず高台または津波避難ビルへ
- 津波避難タワーの位置を事前に把握しておく
- 車避難は渋滞で命を落とすリスクがあるため、徒歩避難を優先
◆行政と地域の連携が鍵
和歌山市は行政主導で避難所整備や物資備蓄を進めていますが、大規模災害では全員を行政だけで守ることは不可能です。
そのため、地域住民同士の自助・共助が復旧のスピードを左右します。
- 自主防災組織や自治会の訓練に参加する
- 避難所運営のサポート役を担う
- 物資の受け渡しや安否確認ネットワークを構築する
◆家庭でできる具体的な備え(チェックリスト)
食料・水
- 水:1人1日3リットル×7日分
- 保存食:レトルト、缶詰、栄養補助食品
非常用品
- 懐中電灯、予備電池、モバイルバッテリー
- 携帯ラジオ(手回し充電式推奨)
- 簡易トイレ・消臭袋
避難用具
- 非常持ち出し袋(リュック)
- 防寒具・雨具
- 笛(閉じ込められた際に使用)
個人用品
- 常備薬・お薬手帳
- 生理用品・衛生用品
- 眼鏡・補聴器の予備
◆過去の地震の教訓を忘れない
和歌山市周辺は歴史的にも大きな地震・津波被害を繰り返しています。
- 宝永地震(1707年):津波で市街地壊滅
- 昭和南海地震(1946年):沿岸部で広範囲浸水
- 南海トラフ地震(想定):同規模かそれ以上の被害予測
これらの歴史は、「過去は未来の警告」であることを示しています。
過去の災害から学ぶことは凄く大事です。なぜなら「だいたい同じ場所で同じような被害が起きる」からです。
液状化のリスクがある場所はもともとの地盤が脆弱なので何年経ってもそのリスクは残ります。津波だって防波堤などのハード対策が進んでいなければ昔と同じようは被害が来ることは分かり切っているはずです。
ただ、実際に被害があった地震だけ学べばいいという訳ではありません。
例えば東北の東日本大震災ですが、私の住んでいた鵜住居町は過去に起きた三陸地震津波やチリ地震津波でも津波は来ても東日本大震災レベルではありませんでした。
そして昔の津波の被害を想定した防波堤などのハード対策を進めてきたからこそ私の祖父母の代からは「大きな地震が来ても津波が町を飲み込むことは無い」と教わってきました。
この教えに疑問を持って防災活動をしてきたのが私達、釜石東中学校でした。
過去の災害は一つの基準であって、それと同じとは限らない。それ以上かもしれない。
この記事を読んで下さった方々には念頭に置いて欲しいことがあります。
「行政に頼らず、自分の命は自分で守る」
という意識を持って頂きたいです。
そういった意識を持ちたいけど、何からしたらいいか分からない方は…
- 東日本大震災語り部防災士のブログを読む!
- ブログ内のお問い合わせから気軽に質問する!
- 東日本大震災の語り部を聞いてみたい!
というアクションをオススメします!
語り部を聞いてみたいという方は是非お問い合わせまで宜しくお願いします!