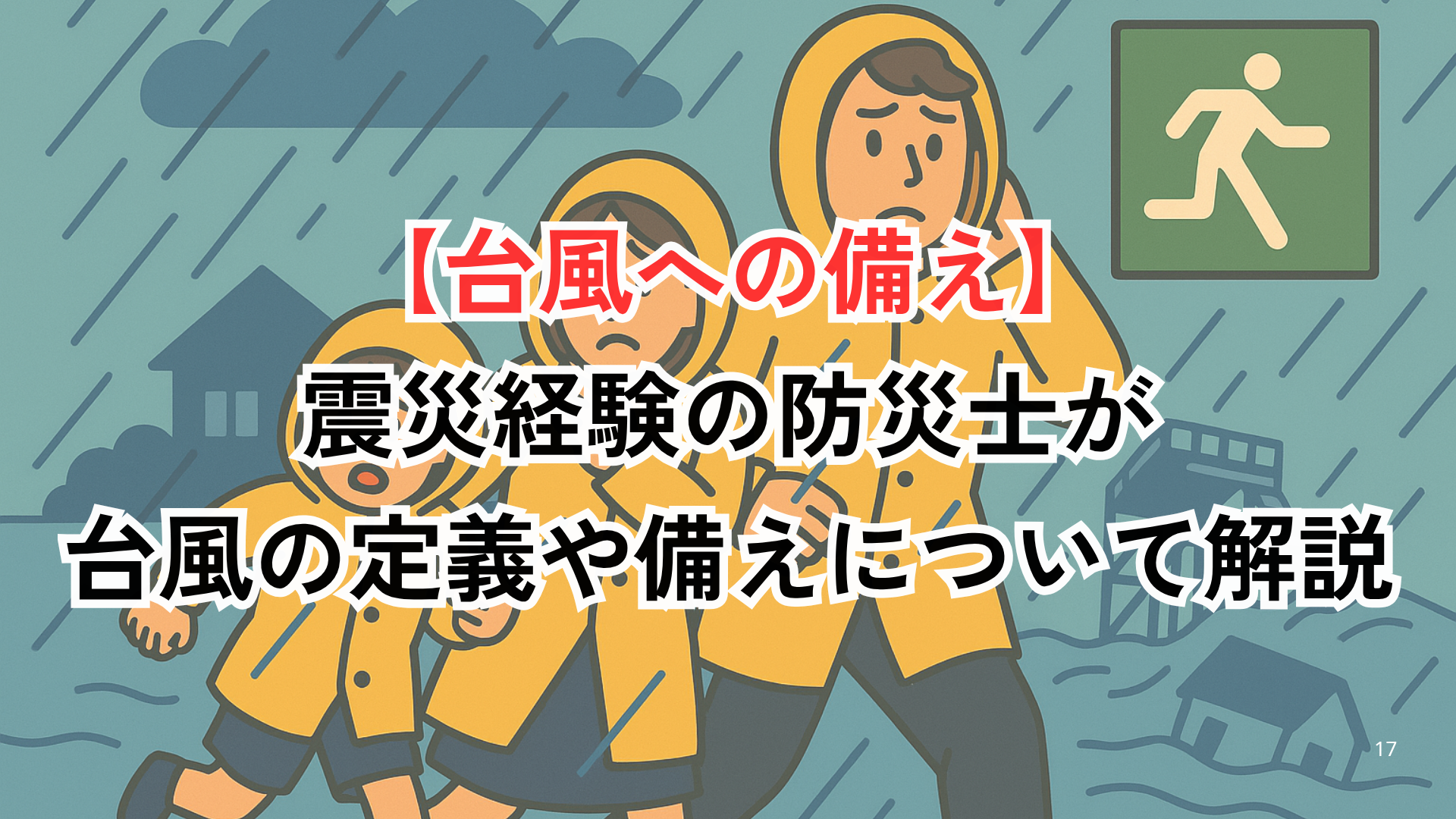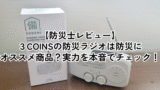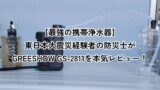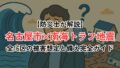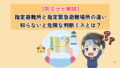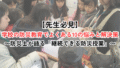第1章:台風の基準は?どのレベルから「台風」と呼ばれるのか?
「台風の定義は?」 熱帯低気圧との違い
台風は「ただの強い雨や風」ではありません。気象庁の定義によると、北西太平洋または南シナ海で発生する熱帯低気圧のうち、最大風速が17.2m/s以上のものを「台風」と呼びます。
ここで重要なのは「熱帯低気圧」との違いです。
| 区分 | 最大風速基準 | 呼び方 |
|---|---|---|
| 熱帯低気圧 | 17.2m/s未満 | 熱帯低気圧 |
| 台風 | 17.2m/s以上 | 台風 |
台風は必ず熱帯低気圧から生まれ、成長して勢力を強めていくのです。
台風の階級 ― 強さをどう表現するか
台風はさらに「どのくらい強いのか」でランク分けされます。気象庁の基準を整理すると次の通りです。
| 区分 | 最大風速の基準 | 被害のイメージ |
|---|---|---|
| 強い台風 | 33m/s以上~44m/s未満 | 屋根瓦や看板が飛ぶ、樹木が倒れる |
| 非常に強い台風 | 44m/s以上~54m/s未満 | 鉄骨建築でも損壊、広範囲の停電 |
| 猛烈な台風 | 54m/s以上 | 住宅が倒壊するレベル、甚大な被害 |
ニュースでよく耳にする「非常に強い台風」「猛烈な台風」という表現は、この基準によるものです。
「暴風域」と「強風域」の違い
台風情報では「暴風域に入りました」「強風域が接近中です」といった言葉が使われます。両者の違いを表にまとめると一目でわかります。
| 区分 | 風速基準 | 危険度・行動目安 |
|---|---|---|
| 強風域 | 15m/s以上 | 自転車は転倒しやすい、車の運転注意 |
| 暴風域 | 25m/s以上 | 屋外行動は危険、飛来物による事故の恐れ |
「暴風域=極めて危険な範囲」と理解しておきましょう。
台風の規模 ― 大きさと強さは別物
台風には「強さ」だけでなく「大きさ」もあります。これは風速15m/s以上の強風域の半径で表されます。
| 区分 | 強風域の半径 | 特徴 |
|---|---|---|
| 大型台風 | 500km以上~800km未満 | 広い範囲で影響、移動に時間がかかる |
| 超大型台風 | 800km以上 | 日本全体が影響範囲に入ることも |
「強さ=風の勢い」「大きさ=影響範囲」と覚えるとわかりやすいです。
世界の呼び方と違い
日本では「台風」と呼びますが、世界では地域ごとに呼び方が異なります。
| 地域 | 呼び方 | 共通点 |
|---|---|---|
| 北西太平洋 | 台風 | 熱帯低気圧が発達したもの |
| 北大西洋・北東太平洋 | ハリケーン | 同上 |
| インド洋・南太平洋 | サイクロン | 同上 |
同じ現象でも呼び名が違うだけ。分類基準や警戒レベルは国ごとに少しずつ異なります。
台風の発生数と季節
気象庁の統計によると、日本のある北西太平洋では年間で約25個前後の台風が発生し、そのうち平均で約3個が日本に上陸します。
- 発生は5月頃から始まり、10月~11月も注意が必要
- シーズンのピークは 8月~9月
夏の終わりから秋にかけては、常に台風に備える意識が必要です。
台風が危険な理由 ― 強風だけじゃない
台風の被害は「風」だけではありません。主に次の3つが大きなリスクをもたらします。
| 被害要因 | 内容 | 具体的な影響 |
|---|---|---|
| 強風 | 建物被害、飛来物、転倒事故 | 屋根瓦・看板が飛ぶ、停電 |
| 大雨 | 河川氾濫、土砂災害、都市型水害 | 広範囲の浸水、住宅損壊 |
| 高潮 | 沿岸部の浸水 | 津波に似た大規模浸水 |
近年は特に「大雨による被害」が深刻化しています。
大雨になることで土壌がぬかるみ、土砂崩れが起きやすい状態になります。
具体例でみる台風の脅威
過去の台風被害から学べる点も多いです。
- 伊勢湾台風(1959年):高潮で甚大な被害、死者・行方不明者5,000人超
- 平成30年台風第21号(2018年):関西空港浸水、都市部ライフライン被害
- 令和元年東日本台風(2019年):堤防決壊・広範囲浸水、「雨」の脅威を再認識
まとめ
- 台風は「最大風速17.2m/s以上の熱帯低気圧」
- 強さは「強い・非常に強い・猛烈な」で区分される
- 「暴風域(25m/s以上)」は極めて危険、外出は控えるべき
- 大きさは「強風域の広さ」で分けられ、大型や超大型も存在する
- 世界では「ハリケーン」「サイクロン」と呼ばれるが現象は同じ
- 日本には年間25個前後発生し、3個前後が上陸する
- 被害要因は「風・雨・高潮」の3つ
- 過去の大災害も雨や高潮の影響が大きかった
第2章:台風が近づいたら何を備えればいい?
台風は事前に進路や規模がある程度予測できるため、事前の備えが命を守るカギになります。ここでは、家庭でできる準備や避難時に必要なものを、分かりやすく整理していきます。
台風前に家庭で備えておくべきもの
台風接近時は停電や断水、物流のストップが起こることがあります。特に風雨で外出できなくなる可能性もあるため、「家にこもる前提」で準備を進めることが重要です。
家庭備蓄のポイント
| 備えの種類 | 具体的な例 | ポイント |
|---|---|---|
| 水 | 1人1日3L×3日分(最低9L/人) | 飲料水と生活用水を分けて用意 |
| 食料 | レトルト食品、缶詰、乾パン、カップ麺 | 調理不要・日持ちするものを優先 |
| 停電対策 | 懐中電灯、乾電池、モバイルバッテリー | ロウソクよりもLEDライトが安全 |
| 衛生用品 | ウェットティッシュ、簡易トイレ、生理用品 | 水が使えない前提で考える |
| 情報収集 | 防災ラジオ、予備の電池 | スマホは停電時に使えない可能性あり |
台風が直前に迫ったときの防災アクション
台風接近直前には、家や生活空間を守るための行動も欠かせません。
家の外でやるべきこと
- 飛ばされそうなもの(植木鉢、物干し竿、ゴミ箱)を片付ける、もしくは固定する
- 雨戸やシャッターを閉める
家の中でやるべきこと
| 行動 | 理由 |
|---|---|
| 懐中電灯やラジオをすぐ使える場所に置く | 停電してから探すのは危険 |
| スマホを満充電にする | 情報収集・連絡手段を確保 |
| 浴槽に水をためる | 断水時の生活用水になる |
| カーテンを閉める | 窓ガラスが割れた際の飛散防止 |
避難行動の準備
台風によっては、自宅にとどまるよりも避難所に移動した方が安全なケースもあります。特に洪水や土砂災害の危険地域では、早めの避難が重要です。
地域ごとのリスクや避難所を確認するために用いるのがハザードマップです。
ハザードマップを確認することで災害リスクの内容と範囲を確認することができます。
各市町村で出しているハザードマップや国土交通省が運営している「ハザードマップポータルサイト」などもあります。
ハザードマップを見て台風の影響で土砂災害や高潮の危険性が上がる地域なのか?避難所はどこなのか?を確認しましょう。
こちらの記事ではハザードマップポータルサイトの使い方をまとめています。是非ご覧ください。
また、よく「避難所」と「避難場所」を間違える人がいます。
その違いはこちらの記事で解説しています。是非読んでください!
避難時に持ち出すもの(防災リュックの中身)
避難時に持ち出すものは基本的には防災リュックに入れましょう。
リュックは両手を自由に動かせて、走りやすいため避難時の収納バックとして推奨する形状です。
その防災リュックの中に最低でもこれは入れた方がいいという物を表にまとめました!
| カテゴリー | 必需品 | ポイント |
|---|---|---|
| 貴重品 | 現金、保険証、身分証 | 停電でキャッシュレスが使えないことも |
| 生活用品 | マスク、ティッシュ、タオル | 避難所生活を快適にする工夫 |
| 非常食 | 飲料水、栄養補助食品 | 軽くて持ち運びやすいもの |
| 衛生用品 | 携帯トイレ、ウェットティッシュ | 避難所ではトイレが混雑しやすい |
| 情報収集 | ラジオ、モバイルバッテリー | 家族との安否確認にも必要 |
まとめ
私は東日本大震災のとき、まさか自分が被災するとは思いませんでした。台風でも同じで、「自分の家は大丈夫」と思い込むことが一番のリスクです。
特に台風は事前に備える時間がある災害です。食料や水を準備するだけでなく、「停電したら?」「避難したら?」とシミュレーションしておくことが命を守ります。
- 家庭備蓄は「3日間×人数分」を基本にする
- 台風直前には「外の片付け」と「家の中の安全確保」を忘れない
- 避難所に行く可能性も考えて、防災リュックを準備
- 命を守る為に「自分は大丈夫」という思い込みをなくすことから始まる
- ハザードマップを見て土砂災害や高潮などのリスク有無と避難所を確認する
第3章:台風と大地震・津波被害の共通点と違い
一見すると「台風」と「地震・津波」はまったく違う災害に思えます。
台風は気象現象によって発生し、地震や津波は地殻変動によって起きる──確かに原因は異なります。
しかし、防災士の視点から見ると「被害の現れ方」や「命を守るために大切なこと」には、共通点も違いもあるのです。
共通する被害パターン
台風と地震・津波は、いずれも人命や生活基盤を直撃する災害です。
| 共通する被害 | 台風の場合 | 地震・津波の場合 |
|---|---|---|
| 建物被害 | 強風による屋根の飛散、浸水による損壊 | 揺れによる倒壊、津波による浸水・流失 |
| ライフライン停止 | 停電・断水・通信障害 | 同様に停電・断水・通信障害 |
| 交通機能の麻痺 | 冠水・倒木・土砂崩れで道路遮断 | 崩落・液状化・津波で道路・鉄道が寸断 |
| 避難生活 | 洪水・浸水による避難所生活 | 余震・津波警戒による避難所生活 |
共通点は「暮らしを支える基盤が一気に止まる」ということです。
台風と地震・津波の違いから見える特徴
共通点がある一方で、台風と地震・津波には明確な違いもあります。
| 観点 | 台風 | 地震・津波 |
|---|---|---|
| 発生予測 | 数日前から進路・規模の予測が可能 | 突発的に発生、予測困難 |
| 備える時間 | 数時間~数日間の猶予がある | ほぼゼロ。揺れや津波は即座に来る |
| 被害の広がり | 主に風・雨による広範囲の浸水や停電 | 揺れによる局所的被害、津波は広域に壊滅的被害 |
| 避難行動 | 事前に余裕を持って避難できる | 揺れや津波発生後、即座に避難行動が必要 |
| 頻度 | 毎年のように発生(季節災害) | 数十年〜数百年に一度の規模もある |
台風は「備える時間がある災害」、地震・津波は「突然襲ってくる災害」と整理できます。
東日本大震災を経験した私から言わせると台風のように備える時間がある災害で人的被害が発生した場合はほぼ人災だと思います。
備えられるなら備えて下さい。自分の命を大切にしましょう。
心理面での共通点
災害時には、人は誰しも「自分は大丈夫」という正常性バイアスの心理に陥りがちです。
この心理は、台風でも地震でも津波でも同じように現れます。
よくある思い込み
- 台風:「うちは内陸だから浸水しない」
- 地震:「築年数が浅いから倒壊しない」
- 津波:「ここまでは津波は来ないだろう」
この油断が、どの災害でも命を危険にさらす大きな要因になります。
守れた命を自分の慢心で守れなかったとなると後悔が残ります。
備えに共通するポイント
台風・地震・津波は違う災害ですが、備えの基本は共通しています。
| 共通の備え | 理由 |
|---|---|
| 家庭備蓄(水・食料・衛生用品) | 災害の種類を問わず、ライフライン停止に直結 |
| 避難経路の確認 | 浸水でも津波でも揺れでも、逃げ道がなければ命は守れない |
| 情報収集手段(ラジオ・モバイルバッテリー) | 災害時はスマホが使えなくなる可能性が高い |
| 家族との安否確認ルール | バラバラのときにどう連絡をとるか決めておく |
| 家の耐震・耐風・防水対策 | 建物そのものを守ることが最初の防災 |
東日本大震災を経験した私が上記表に当てはまる中でオススメする防災商品について紹介しています!
是非、備えの参考にしてください!
まずはオススメのラジオを紹介します!ラジオはSNSよりも正確で早い情報を収集できます。東日本大震災の時にも私が親と再会することができたのはラジオのおかげでした!
自然災害時の水問題ですが「備蓄していた飲料水がそこを尽きてしまった場合どうしよう」と考えたことがあると思います!そんな時にぜひ持っていて欲しいのが浄水器です!かなりオススメな浄水器があるので下の記事からご覧ください!
私は東日本大震災の被災者として、地震と津波の恐ろしさを肌で経験しました。
そして防災士として活動する中で、台風被害に遭った人々の声も聞いてきました。
共通して言えるのは、「災害の種類は違っても、生活が止まる苦しさは同じ」だということです。
例えば震災後、避難所では水や食料をめぐる不安が続きました。
台風被害でも、同じように停電や断水が長引き「水がない」「スマホが充電できない」といった声が上がります。
つまり、どんな災害であれ「事前の備え」があれば安心できる時間を確保できます。
逆に備えがなければ、災害の種類に関係なく生活は一気に立ち行かなくなるのです。
まとめ
- 台風と地震・津波は「生活基盤を止める」という点で共通
- 台風は「備える時間がある災害」、地震・津波は「突然襲う災害」という違いがある
- 「自分は大丈夫」という油断は、すべての災害で命を危険にさらす
- 防災の基本(水・食料・情報収集・避難計画)は共通して役立つ
第4章:語り部防災士の視点から語る台風への備え
私は中学1年生のとき、岩手県釜石市で東日本大震災を経験しました。
「釜石の奇跡」と呼ばれた避難行動の当事者であり、今も防災士として各地で語り部活動を続けています。
その中で気づいたのは、災害の種類は違っても「備え」の本質は同じだということです。
ここでは私の体験や学びを交えながら、台風に対する備えについてお話しします。
「予測できる災害」とどう向き合うか
地震や津波は突然やってきます。震災のときも「あと数秒で逃げられるかどうか」が生死を分けました。
一方で台風は、数日前から進路や規模が予測されます。
つまり、台風は「備える時間がある災害」なのです。
- 食料や水を買っておく時間がある
- 家の外回りを片づける時間がある
- 避難するかどうかを判断する時間がある
この「時間の余裕」を活かすことが、台風から命を守る最大のポイントだと私は考えています。
台風でよく聞く後悔
防災講演の場やニュースなどで「台風で被害を受けた人」の声を聞くと、よく出てくる後悔があります。
| 後悔の声 | 具体例 |
|---|---|
| 備え不足 | 「水が買えなかった」「モバイルバッテリーを充電していなかった」 |
| 判断の遅れ | 「避難しようと思ったら道が冠水していた」 |
| 思い込み | 「うちは大丈夫だと思って何もしなかった」 |
この3つは、東日本大震災での声とも重なります。災害の種類を問わず、「備えなかったこと」が一番の後悔になるのです。
私が台風に備えていること
私は防災士としてではなく「一人の生活者」として、台風が近づくと必ず次のことを確認しています。
| 備え | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 家庭備蓄 | 水・食料を3日分以上 | 台風は物流が止まりやすい |
| 停電対策 | モバイルバッテリー・懐中電灯を充電 | 情報収集と生活の両方を支える |
| 避難判断 | 自宅周辺のハザードマップを確認 | 浸水リスクがあれば早めに避難 |
| 家族との連絡 | 災害用伝言ダイヤルや集合場所を確認 | 離れていても安心できるように |
| 家の安全対策 | 窓の補強、飛散物の片づけ | 「風」と「水」両方を意識する |
ポイントは「命を守るために最低限必要なこと」を、台風が来る前に終わらせておくことです。
台風に限らず一度準備をすることで今後「どんな自然災害に対しても備えた状態」になります。
語り部として伝えたいこと
震災のとき、私が強く感じたのは「自分だけは大丈夫」という思い込みが一番危険だということです。
台風でも同じで、「この程度の雨なら平気」「避難するほどじゃない」「この場所は危険じゃない」と考えてしまいがちです。
でも、その油断が命を危険にさらします。
逆に「少しでも危ないと思ったら行動する」人は助かる確率が高いのです。
語り部として私はいつも、「命より大切なものはない」と伝えています。
台風が来る前に少しでも備えておくこと、それが大切な家族や自分を守ることにつながります。
まとめ
- 台風は「備える時間がある災害」。その時間をどう使うかが生死を分ける
- よくある後悔は「備え不足」「判断の遅れ」「思い込み」
- 家庭備蓄・停電対策・避難判断・家族の連絡ルールは必須
- 語り部として強調したいのは「命より大切なものはない」ということ
正直、釜石東中学校の防災教育を受けていなければ私はあの日で亡くなっていました。
当時を生き残った者だからこそ、この経験を後世に伝承する必要があります。
台風と地震・津波は災害の種類が違いますが備え方は一緒です。
ぜひ、実際に津波から逃げた人の経験談を参考して頂けたら幸いです。
この記事を読んで下さった方々には念頭に置いて欲しいことがあります。
「行政に頼らず、自分の命は自分で守る」
という意識を持って頂きたいです。
そういった意識を持ちたいけど、何からしたらいいか分からない方は…
- 東日本大震災語り部防災士のブログを読む!
- ブログ内のお問い合わせから気軽に質問する!
- 東日本大震災の語り部を聞いてみたい!
というアクションをオススメします!
語り部を聞いてみたいという方は是非お問い合わせまで宜しくお願いします!