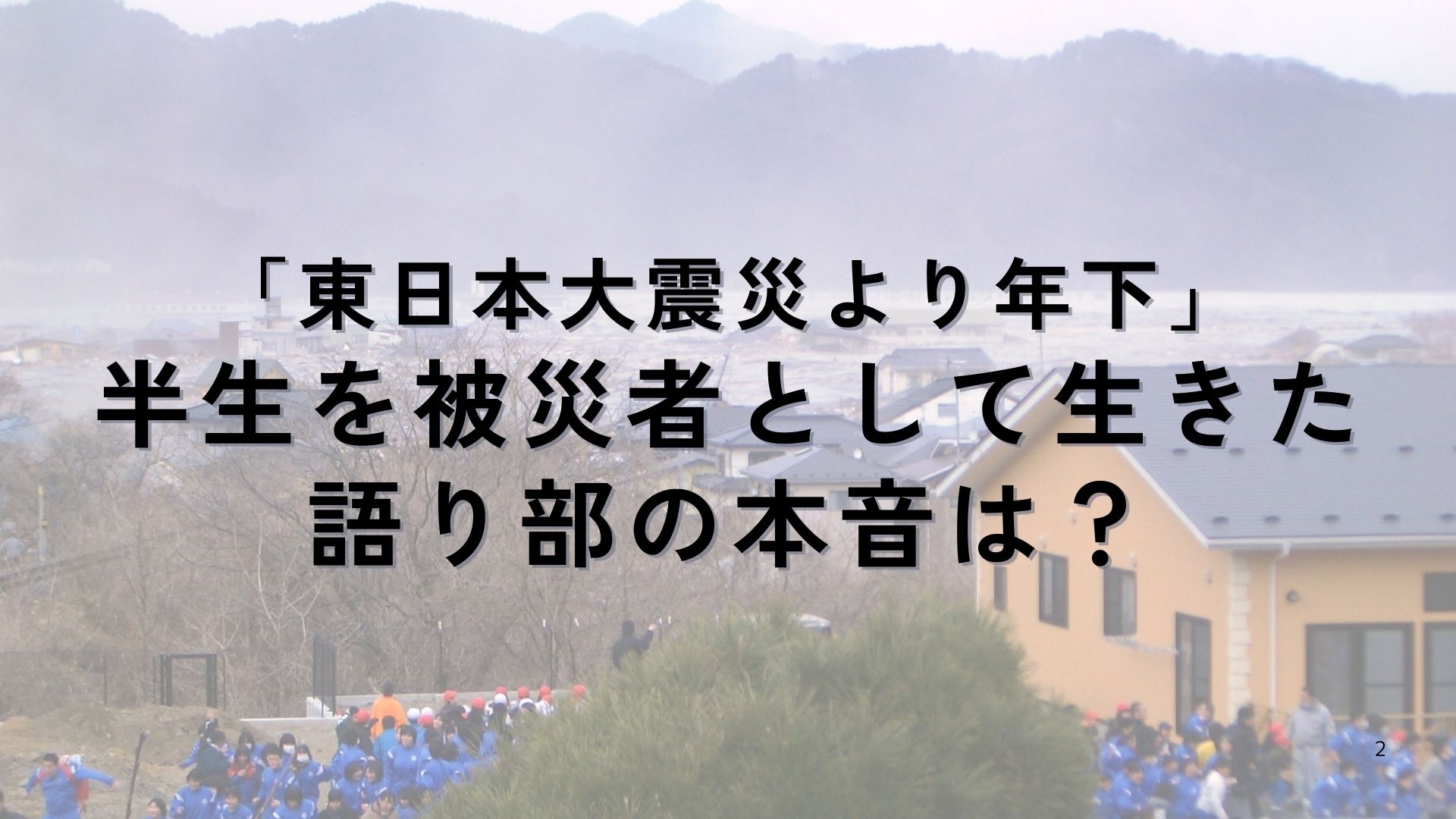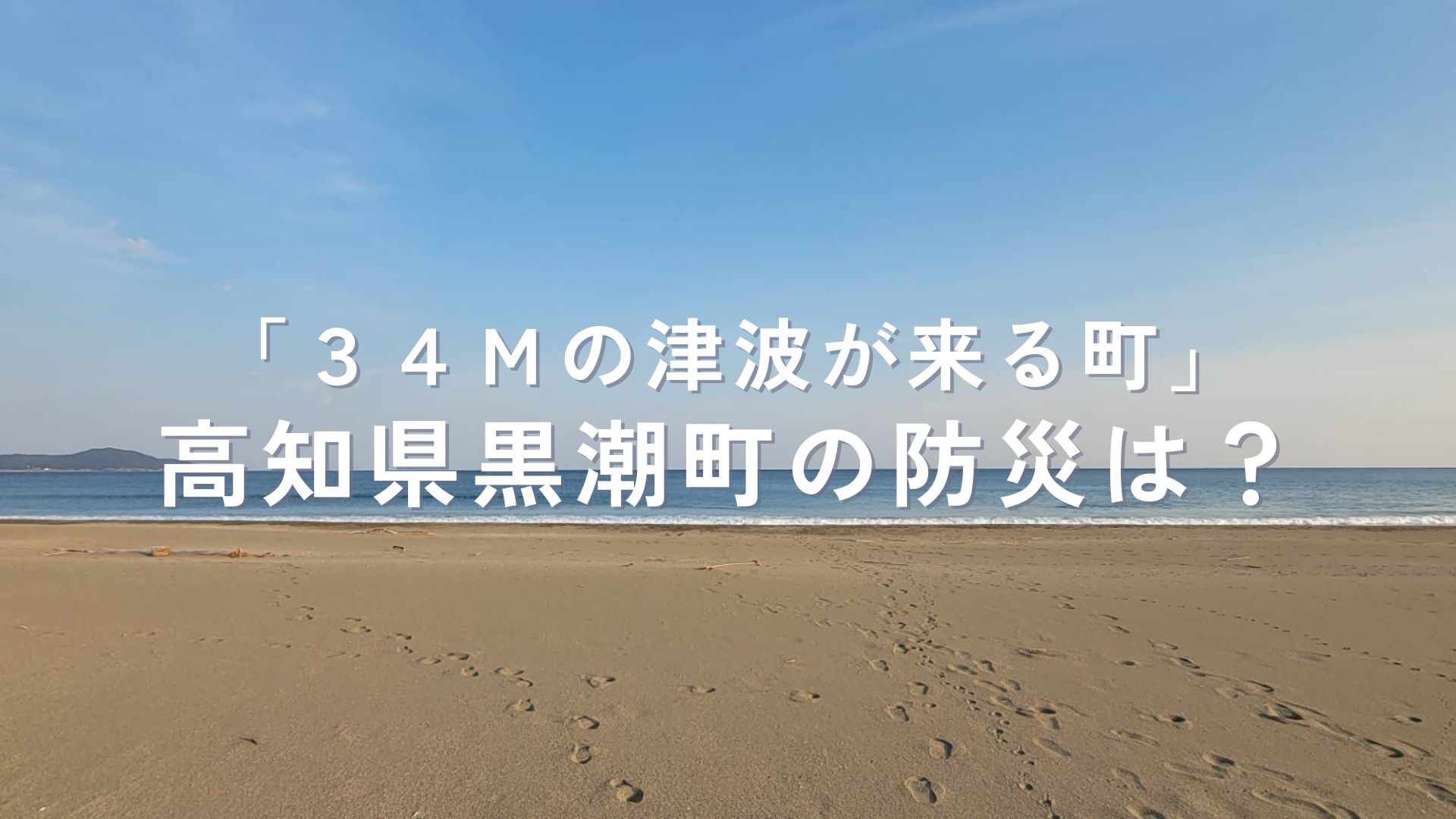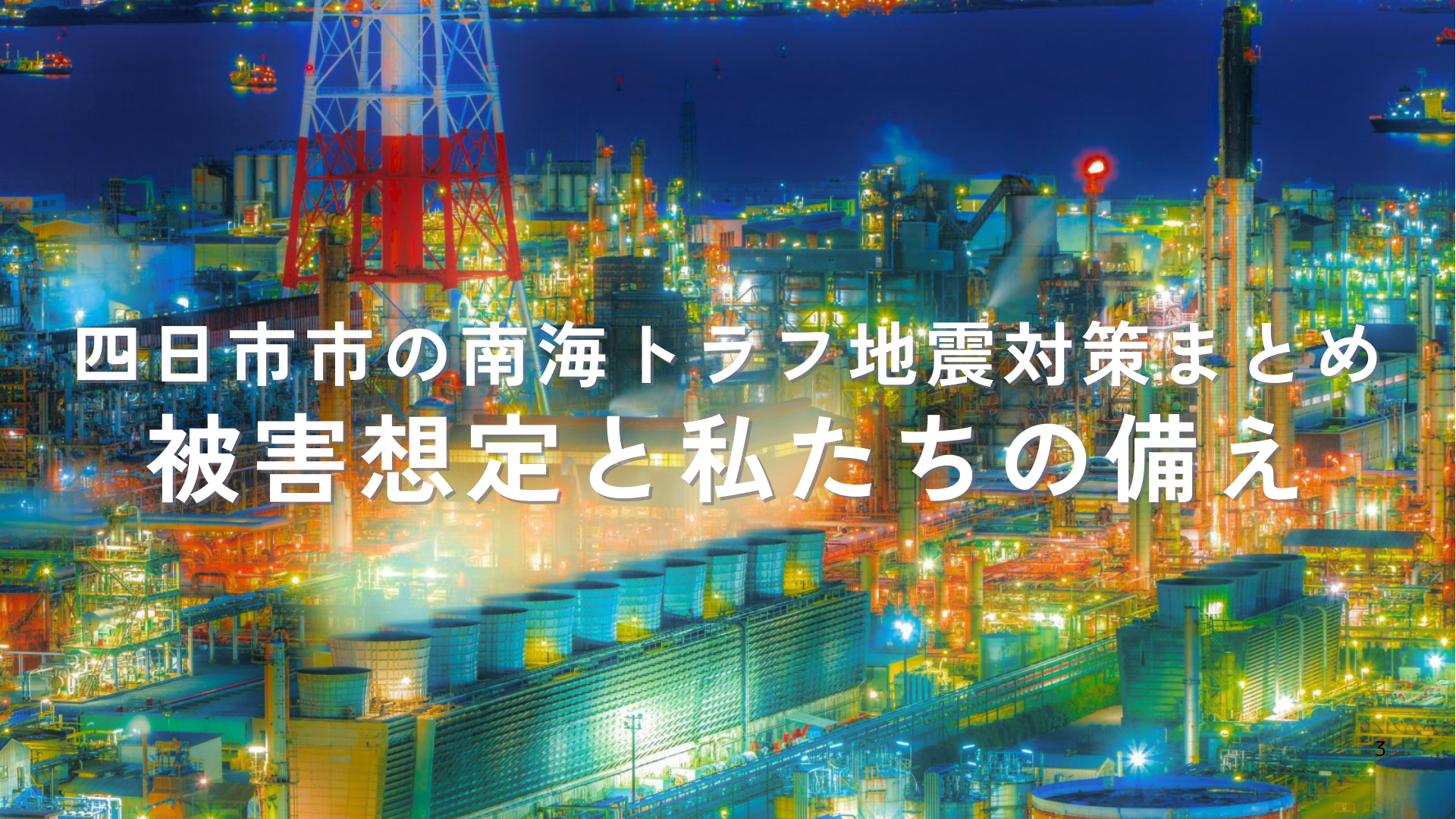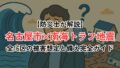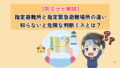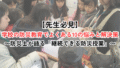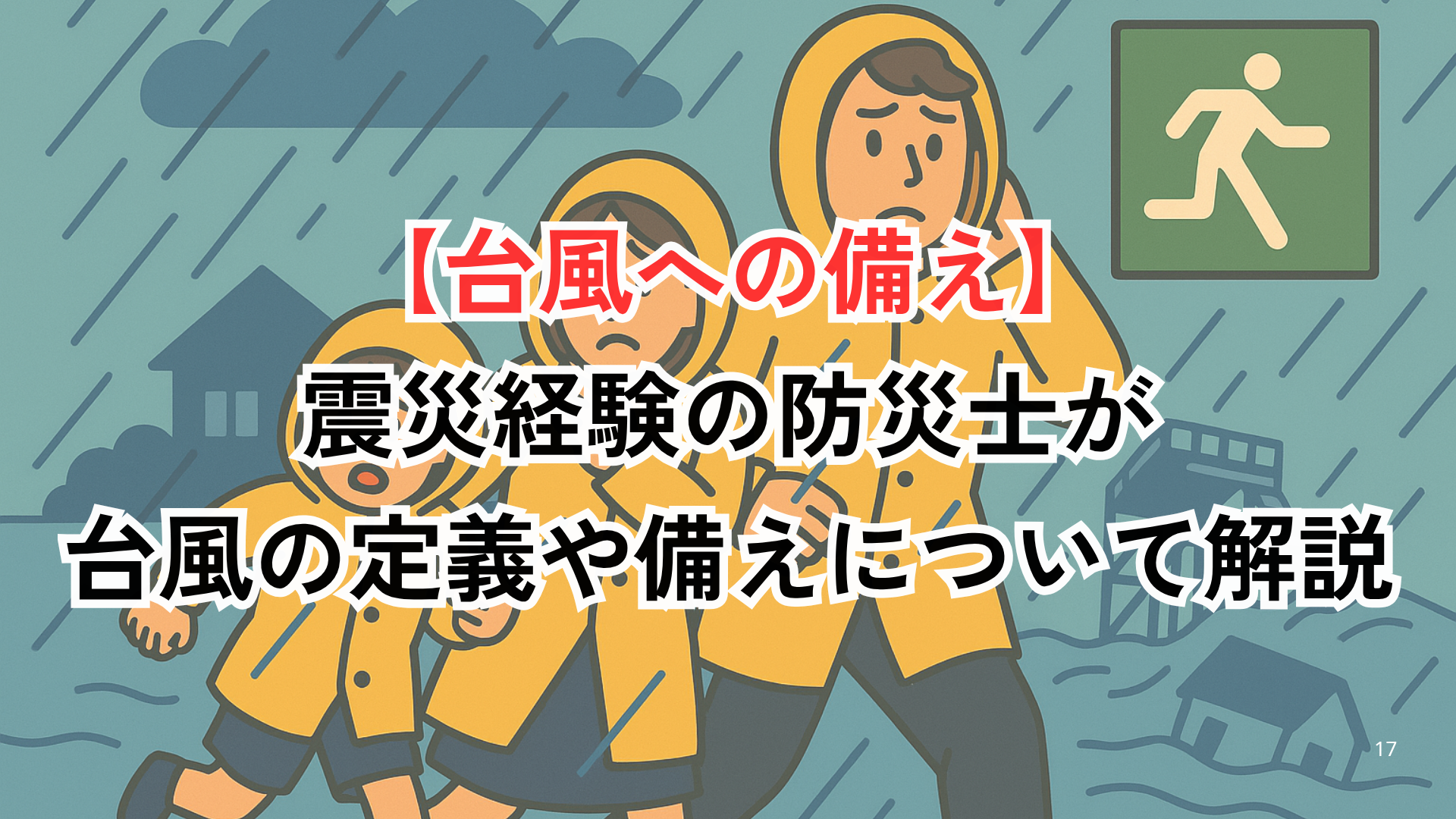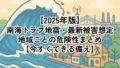第1章:東日本大震災を経験して・・・
2011年3月11日 東日本大震災が発生した際に私は岩手県釜石市に住んでいました。
「釜石の奇跡」と呼ばれる釜石東中学校に通っており、地震直後にすぐに避難を開始して小学生や地域住民と一緒に津波から逃げて生き延びることが出来た当事者です。
多くのメディアに「釜石の奇跡」と称されて防災教育を評価されてきました。
ただ、私は学校から離れていた大切な人を東日本大震災で亡くしてしまいました。自分が防災教育を受けていても周囲の人に共有しないと大切な人を助けることが出来ないと学んだ中学生の時から東日本大震災の体験談を伝える「語り部」という活動をしています。そして防災士の資格も取得して活動をしております。
そんな私ですが本日は
「そもそも南海トラフ地震ってなんなの?」
「過去にも似たような地震はあったの?」
「東日本大震災と比べてどっちが被害が酷いの?」
「何を備えたらいいの?」
という疑問を持った方がに対して南海トラフ地震について説明致します!
第2章:南海トラフ地震ってなに?
さて、今回のテーマである「南海トラフ地震」。ニュースや特集番組などで耳にしたことがある方も多いかと思います。でも、「どこで起きるの?」「何が怖いの?」という部分まで知っている人は意外と少ないんです。
南海トラフとは、静岡県沖から九州沖にかけて延びる海底の溝(プレートの境界)です。ここではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいて、その境界で巨大なエネルギーが溜まり続けています。

このエネルギーが限界を超えたとき、一気に解放されて地震が起きる。これが南海トラフ巨大地震です。
第3章:実は何度も起きている「南海トラフ地震」
南海トラフの地震は、100〜150年周期で繰り返し起きていることがわかっています。
たとえば、
- 1707年 宝永地震(M8.6〜8.7):南海・東海・東南海が一斉に動き、津波とともに甚大な被害。富士山が噴火したのもこの直後です。
- 1946年 昭和南海地震(M8.0):終戦直後の混乱期に発生。津波と倒壊で1,300人以上の命が失われました。
つまり、南海トラフ地震は「いつか起きる」ではなく「必ず起きる」もの。そして現在、前回の地震からすでに70年以上が経過しています。そろそろ次が来てもおかしくない…と専門家たちは警鐘を鳴らしているんです。
政府の地震調査委員会では発生確率が70~80%でしたが2025年1月15日に「80%程度」に引き上げられました。理由としては時間の経過による引き上げとなっております。
ハッキリした違いが分かりませんが70%が消えた時点で確実に少しづつ発生確率は上がっていると捉えられます。
第4章:東日本大震災と何が違うの?
地震のタイプは、どちらも「プレート境界型地震」です。でも、被害の出方や想定されるリスクには違いがあります。
東日本大震災では、太平洋プレートが沈み込むことで東北の海底が跳ね上がり、巨大津波が発生しました。
南海トラフ地震では、西日本側の広い範囲(静岡〜九州)で同時多発的に地震が起き、大きな揺れと津波が襲うと想定されています。
さらに違うのは、「大都市への影響」。
南海トラフの想定被災地には、大阪、名古屋、静岡、そして四国や九州の都市が含まれているんです。つまり、日本の経済の中枢が直撃される可能性が高い。
つまり高速道路や東海道新幹線などインフラ面に大ダメージが与えられることが予測されます。
この違いは、震災後の復旧や物流にも大きく影響します。
東日本大震災のときも、物資が届かず苦労しましたが、南海トラフ地震ではもっと広範囲で物資が止まる可能性があるのです。
東日本大震災でさえも支援されたご飯を頂けたのは三日後くらいです。それまでは避難した体育館の近くに住む方々が分けて下さったり、停電の影響で冷蔵庫が使えなくなり、肉や野菜などを消費しようと避難所に食材を持って集まって炊き出しなどを行ったりしていました。
だからこそ支援物資に頼ると数日間はご飯を食べられない可能性があります。
では実際、どんな被害が予想されているかは次の章になります!
第5章:想定される被害のリアル
内閣府が発表している最悪の被害想定では…
- 死者:最大32万人
- 津波:最大30m(特に高知県や三重県)
- 建物倒壊・火災・孤立地域:数十万世帯
さらに、
- 交通網の寸断
- 大規模停電
- 情報遮断 などが同時に起きる「複合災害」が想定されています。
いずれも「最悪の場合」を想定した際に発表された数値となっております。
交通網の寸断については先程記載した通りです。
東日本大震災の時は「被害が大きい地域」ほど停電の復旧が遅れました。私はかなり山奥にある祖父母の家で避難生活をしていました。海から離れた場所だったので津波の影響がなく、町の状態も綺麗なままではありましたがその地域に電気が通ったのは震災から約2週間後でした。釜石市内では早い方でした。
高知県黒潮町では34.4mの津波が襲うと予想されています。そして三重県も東海圏内では津波の被害が甚大と予想されています。
各地域についての被害予想や備えについてはこちらの記事にまとめています!
実際に地震が起きた日のことを想像してみてください。
真夜中、雨、家族が別々の場所にいる…そんな最悪の条件下でどう動くか、冷静に考えることが必要です。
第6章:東日本大震災経験者&防災士の私が伝えたい「本当に役立つ備え」
ここで、防災士である私が日頃から心がけている備えをいくつかご紹介しますね。
● 家庭内の備蓄
- 水(1人1日3L × 7日分)できるだけ「~年保存水」などがオススメ!
- レトルト食品、缶詰、カップ麺、乾燥野菜、お菓子
- ガスボンベ、懐中電灯、乾電池
- 簡易トイレ(重要!)
- スマホ用バッテリー
南海トラフ地震程の大地震が起きた際に支援物資を頼りにすることはオススメできません。そもそもの考えたとして私は「自分の命を他人に任せていいのか?」という思考なので自分の命は自分で守るように備えるべきだと思っています。
その中で特に食料関係の備蓄は大切になってきます。水は賞味期限が短いと買い替える頻度が多くなります。普段から浄水器を使用せず、ペットボトルの水を購入している方は自然とローリングストックが出来ている方が多いと思います。そうではない人は出来るだけ保存が効く水を備蓄しておくことで購入頻度が増えるというストレスを軽減して備えることができます!
そして非常食ですが最低3日分。可能であれば1週間分を備えましょう。以前、イベントで語り部をした際に知り合った元防衛省の方とお話をしましたが国は震災発生日を0日とした際に3日目には非常食を届けられるような想定と準備をしていると力強く仰ってくださいました。
だからこそ最低3日分。そして交通網への影響が想定より酷かった場合を考えて可能であれば1週間分を備えることを推奨します!
● 非常用持ち出し袋
- ラジオ(手回し式が便利)
- 常備薬・マスク・下着
- 現金(小銭も)・身分証明書のコピー
- タオル・レインコート・軍手
- 子どもや高齢者がいる家庭は個別のケア用品も忘れずに
ラジオは情報源としてかなり優秀なツールです。実際に私は東日本大震災ではラジオがあったおかげで「~中学校は○○の体育館に避難しています」などの情報が流れて親が迎えに来てくれました。そのあとも支援物資が届く場所や種類、ボランティアの情報など様々な情報を取得することができます。東日本大震災を経験した身からしたらスマホよりもラジオが正確で欲しい情報を取得することが出来るのでオススメします!
● 家族でのルール決め
- 避難場所の確認(昼夜どちらでも対応できるか)
- 連絡方法(災害伝言ダイヤルやSNS)
- ペットの避難方法も考えておくと安心です
上記2つは「生き延びた後の備え」になりますがまずは「生き残るための備え」をしなければなりません。その備えにピッタリ当てはまる防災アクションがあります。それが・・・
「ハザードマップを見る」×「避難訓練をする」
です!危険な場所と安全な場所を把握して、避難場所まで一人で避難できる訓練をすることが大事です!是非ご家族と一緒に話し合って共有して下さい!
オススメなハザードマップは以下の記事になります。
第7章:地域で助け合うということ
私が中学生の時の防災教育では「地域住民との繋がり」を大切にしてきました。
地域住民と繋がりが強くなるにつれて中学生が発信する防災活動に対して地域住民の関心も高まり、結果的には私達中学生が率先して避難することで小学生や地域住民が後を追いかけて避難することで津波から命を守ることが出来ました。
いざっていう時に近隣住民と声を掛け合い、一緒に逃げたり、非常食を分け合ったりすることができます。是非ご近所さんとの繋がりを大切にして下さい。
第8章:命を守るのは、あなた自身
私たちは自然の力には勝てません。でも、被害を減らすことはできます。
大事なのは、「なんとなく怖い」で終わらせず、具体的な行動に移すこと。
準備をしておくことで、あの震災の日のようなパニックを少しでも和らげられるのです。
私たちが備えることは、自分の命を守ることはもちろん、
家族、友人、地域の大切な人たちを守ることにもつながります。
おわりに
南海トラフ地震は明日かもしれないし、10年後かもしれません。
でも確実に、「いつか」はやってきます。
そのときに後悔しないように、今できることを一緒に始めましょう。
「防災は未来への思いやり」
そう信じて、私は今日も防災士として活動しています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。