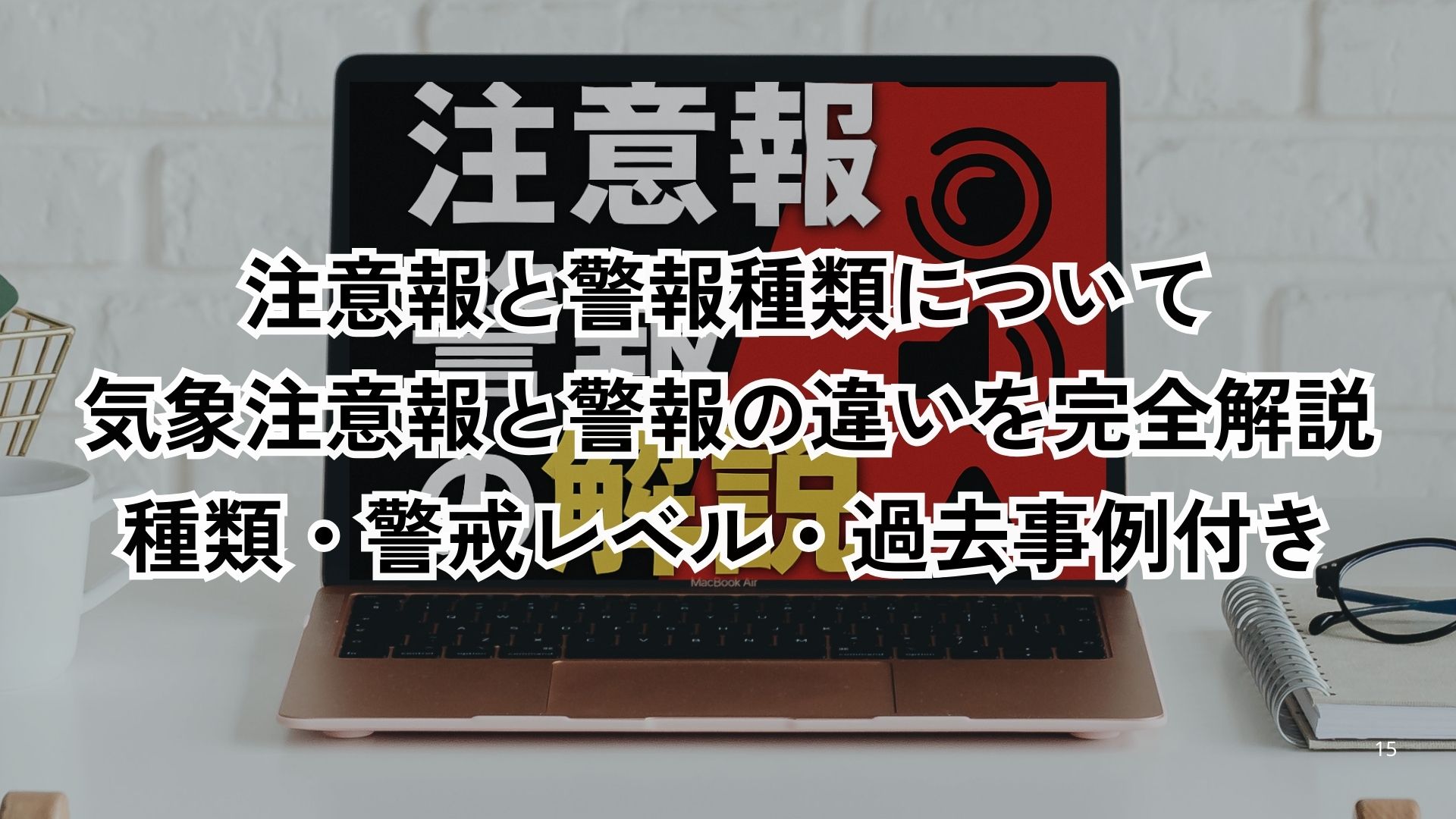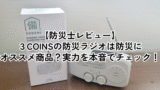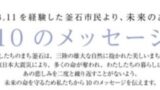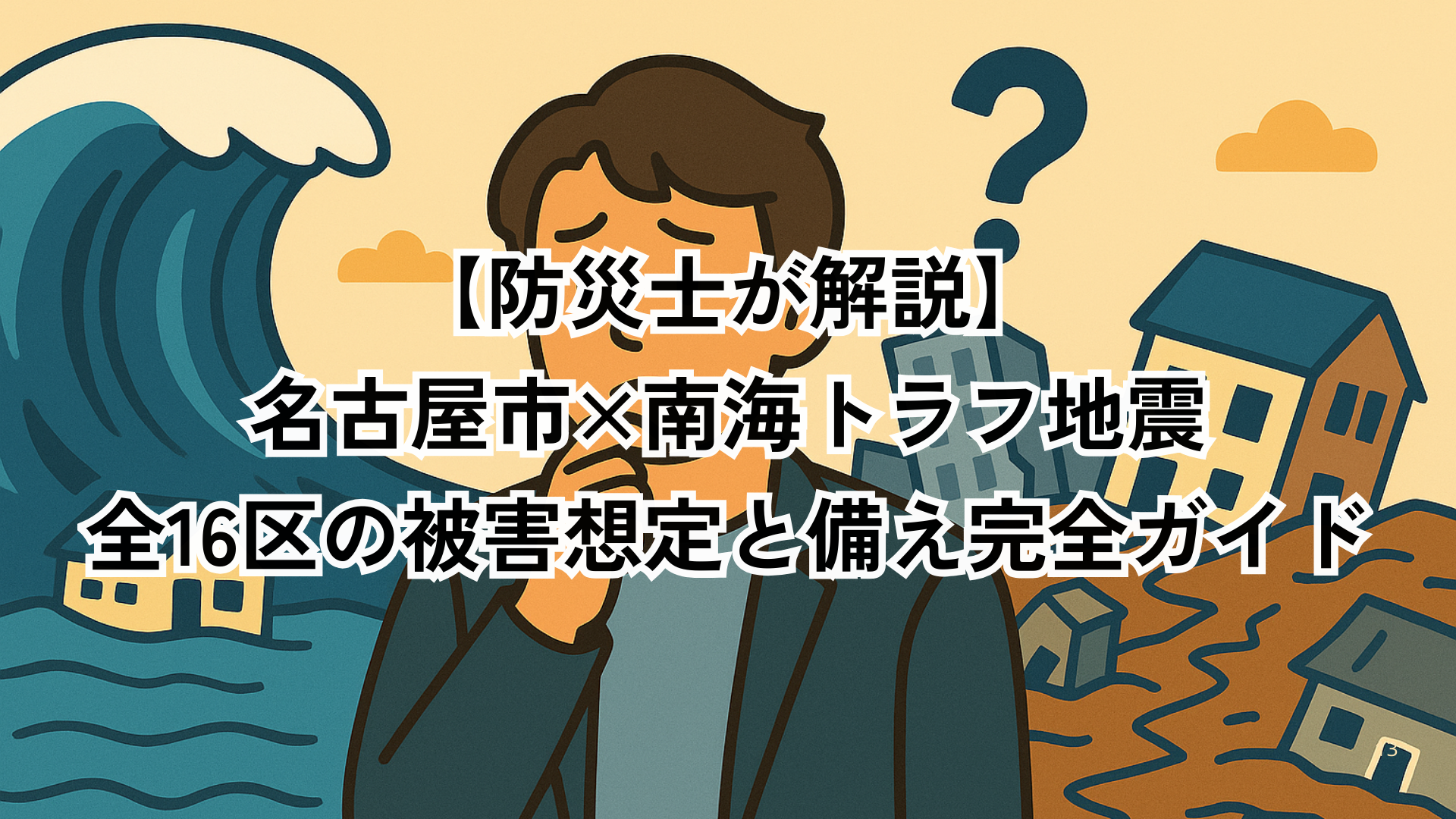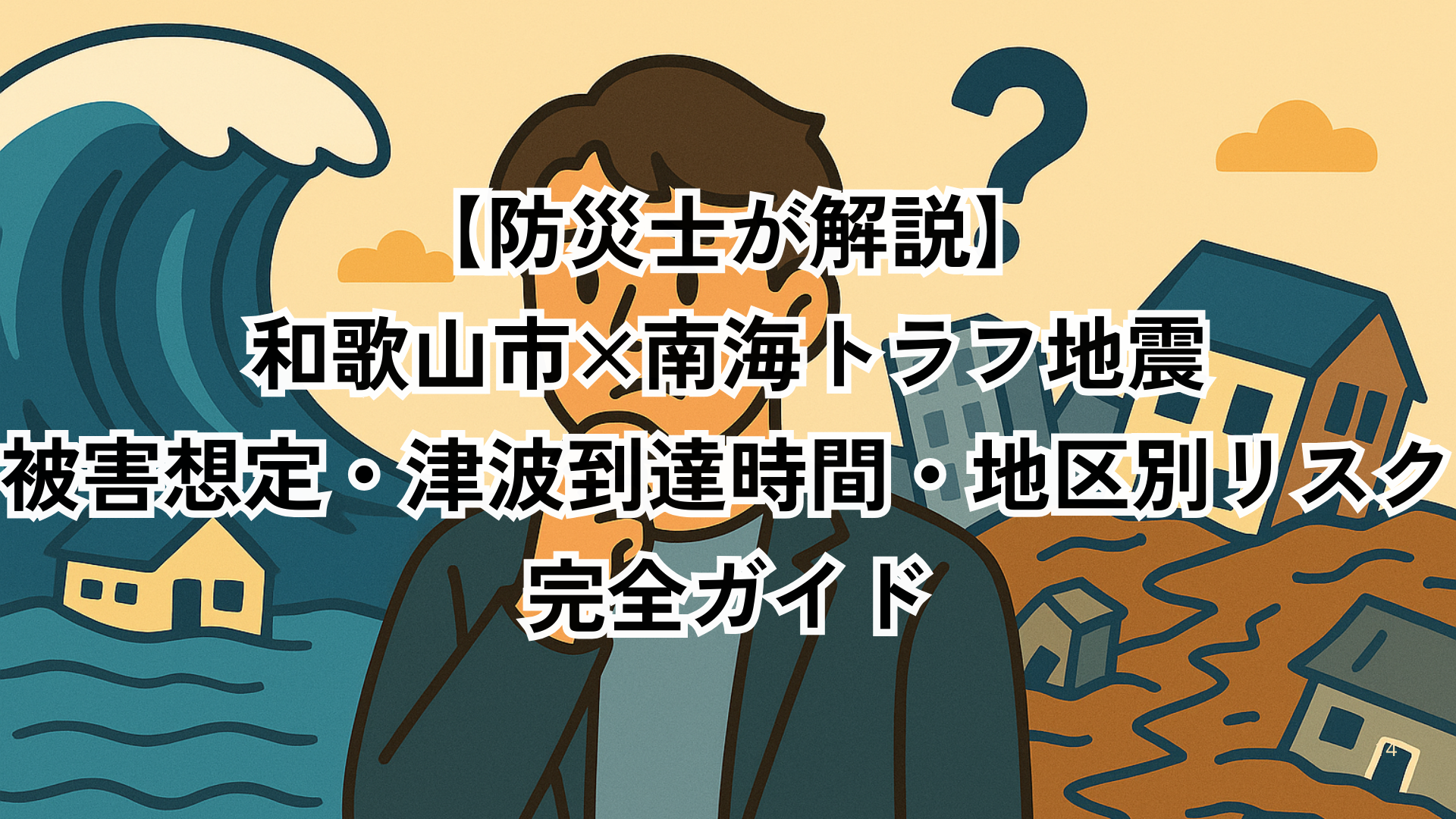第1章 注意報と警報の説明
日本は地震、台風、大雨、大雪、火山噴火など、あらゆる自然災害が発生しやすい国です。
そのため、気象庁や国・自治体は、災害の危険が高まったときに「注意報」や「警報」を発表します。
しかし、実際のところ、
「注意報と警報って何が違うの?」
「特別警報っていつ出るの?」
「警戒レベルっていうのも聞いたことがあるけど…」
という疑問を持っている人も多いはずです。
ここでまず押さえておきたいのが、危険度の階層構造です。
気象情報の危険度は大きく次のように分かれます。
- 注意報 … 被害が出るおそれがあるとき
- 警報 … 重大な災害が起こるおそれがあるとき
- 特別警報 … 数十年に一度の災害の危険が迫っているとき
そして、2019年からはこれらを「警戒レベル」で統一的に表現するようになりました。
これにより、注意報・警報・特別警報が警戒レベル3〜5に紐づき、避難行動の判断がしやすくなっています。
第2章 注意報と警報の種類と内容
ここでは、災害の種類ごとに「種類+意味+発令条件+とるべき行動」を表形式で整理します。
1. 大雨・洪水関連(大雨警報、洪水警報、大雨注意報、洪水注意報)
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 大雨警報 | 大雨によって重大な災害が発生するおそれがある | 1時間・3時間・24時間降水量の予測値が基準を超える | 避難準備、避難開始、河川や斜面から離れる |
| 洪水警報 | 河川の氾濫によって重大な災害発生の恐れがある | 河川水位が氾濫危険水位に達する予測 | 避難、河川付近の立入禁止 |
| 大雨注意報 | 大雨によって災害の可能性が高まっている | 降水量が注意基準を超える | 屋外活動の中止、避難の準備 |
| 洪水注意報 | 河川氾濫の可能性が高まっている | 河川水位が警戒水位に近づく | 水位情報の確認、早期避難準備 |
備えと注意ポイント(リスト形式)
- 事前にハザードマップで浸水・土砂災害警戒区域を確認する
- 家族で避難所の場所と経路を共有する
- 止水板や土のうを備えておく
- 夜間や悪天候時にも避難できるようライトや防水バッグを準備
- 車での避難は原則避け、徒歩や自転車で安全な高台へ移動
- 増水した川や用水路には絶対に近づかない
- 情報は気象庁や自治体の公式発表を優先する
2. 津波・高潮関連(津波警報・注意報、高潮警報・注意報)
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 津波警報 | 高さ1m以上の津波が予想される | 地震・海底火山活動による津波予測 | 直ちに高台や堅牢な建物上階へ避難 |
| 津波注意報 | 高さ0.2m以上の津波が予想される | 同上 | 海岸・河口から離れる |
| 高潮警報 | 高波と満潮が重なり重大被害の恐れ | 気圧・風速・潮位の予測値が基準超え | 海岸から離れ、避難準備 |
| 高潮注意報 | 高潮による浸水可能性 | 同上 | 海岸付近の活動を中止 |
備えと注意ポイント(リスト形式)
- 警報発令と同時に即避難(判断の遅れは命取り)
- 高台や堅牢な建物上階の位置を事前に確認
- 家族の集合場所と連絡手段を決めておく
- 夜間避難用にヘッドライト、防水バッグを準備
- 台風接近時や満潮時刻を確認して行動計画を立てる
- 海辺での釣りや観光は警報発令時に中止する
- 避難は荷物を最小限にし徒歩または自転車で行動
3. 強風・台風関連(暴風警報・注意報)
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 暴風警報 | 平地で風速20m/s以上が予想される | 気圧配置と風速予測 | 屋外活動禁止、屋内安全確保 |
| 暴風注意報 | 強風で被害の恐れ | 同上 | 飛散物対策、外出制限 |
備えと注意ポイント(リスト形式)
- 飛ばされやすい物(植木鉢、物干し竿、自転車)を室内に移動
- 窓ガラスに飛散防止フィルムや養生テープを貼る
- 停電対策にモバイルバッテリー、ラジオ、非常食、水を用意
- 倒木や看板の落下が予想されるエリアを避ける
- 公共交通機関の運休情報を確認し移動計画を変更
- 前日までに安全な場所への移動を検討
- 風向きや暴風域の拡大に注意を払う
4. 大雪・低温関連(大雪警報・注意報、低温注意報)
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 大雪警報 | 積雪による重大災害の恐れ | 積雪量が基準超え | 外出自粛、備蓄確認 |
| 大雪注意報 | 積雪による被害の可能性 | 同上 | 早期対策開始 |
| 低温注意報 | 氷点下による農作物被害や凍結 | 気温予測が基準下回る | 防寒・凍結防止策 |
備えと注意ポイント(リスト形式)
- 食料・水・燃料を数日分確保
- 停電時用に毛布、カイロ、蓄電池を準備
- 車は冬用タイヤやチェーンを装着
- スコップ、防寒着、非常食を車に常備
- 屋根の雪下ろしは安全帯着用、複数人で実施
- 水道管凍結防止のため保温材や水抜きを行う
- 近隣との協力体制を事前に築く
5. 火山関連(噴火警報・注意報)
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 噴火警報 | 火口周辺で噴火の恐れ | 火山性地震、火山性微動の観測 | 直ちに危険区域から退避 |
| 噴火注意報 | 火山活動の活発化 | 同上 | 活動状況の確認と準備 |
備えと注意ポイント(リスト形式)
- 火山防災マップで危険区域と避難経路を確認
- ヘルメット、ゴーグル、防塵マスクを備える
- 火山灰による健康被害・視界不良を考慮し外出を最小限に
- 車や家屋のフィルターを保護
- 火山灰堆積による停電・断水に備えて備蓄を確保
- 気象庁や自治体発表を常時確認
- 観光や登山は状況次第で即中止
6. 地震関連(緊急地震速報)
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 緊急地震速報 | 強い揺れが来る前に知らせる | 震源情報とP波の観測 | 直ちに安全確保行動 |
備えと注意ポイント(リスト形式)
- 速報受信後は即机の下に隠れ頭部を保護
- 家具固定、ガラス飛散防止、非常袋の常備
- 複数の避難経路と集合場所を家族で共有
- 揺れ収まり後は火の始末とブレーカー遮断
- 停電・通信障害に備えてラジオやバッテリーを常備
- 安否確認は171やLINE機能を活用
- 沿岸部では津波警報を確認し即避難
7.その他
| 種類 | 意味 | 発令条件 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| 濃霧注意報 | 視程1km未満 | 視界不良 | 車の減速運転 |
| 雷注意報 | 落雷の恐れ | 雷雲接近 | 屋外活動中止 |
| 乾燥注意報 | 火災発生の恐れ | 湿度30%以下など | 火の取扱注意 |
| なだれ注意報 | なだれ発生の恐れ | 積雪量・気温変化 | 山岳地立入禁止 |
| 霜注意報 | 霜による農作物被害 | 気温低下 | 農作物保護 |
| 地面凍結注意報 | 路面凍結の恐れ | 気温低下 | 車間距離確保 |
以上のように数多くの注意報、警報の種類があります。
今回はよく聞くような注意報と警報についてまとめて紹介しましたがもっと詳しく知りたい方は気象庁の公式サイトからご確認お願いいたします。
第3章 過去の警報発令による自然災害の事例
以下の表は、各警報に関連する代表的な自然災害事例と、その発生場所・日時・要因・被害をまとめたものです。リンクから政府報告書も確認できます。
| 警報種別 | 事例 | 発生場所 | 発生日 | 要因 | 被害範囲 | 死者・行方不明 | インフラ被害 | 報告書リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雨・洪水警報 | 平成30年7月豪雨 | 西日本各地 | 2018年7月 | 梅雨前線停滞+暖湿流 | 西日本11府県 | 死者・行方不明263人 | 家屋3万棟以上浸水 | 内閣府PDF |
| 津波警報 | 東日本大震災 | 東北地方太平洋沿岸 | 2011年3月11日 | M9.0地震 | 東北〜関東沿岸 | 死者・行方不明1.8万人超 | 港湾・住宅壊滅 | 気象庁報告 |
| 高潮警報 | 伊勢湾台風 | 東海地方中心 | 1959年9月26日 | 台風+高潮 | 愛知・三重 | 死者5098人 | 港湾・住宅壊滅 | 防災白書 |
| 暴風警報 | 台風21号(2018) | 近畿地方 | 2018年9月4日 | 大型台風直撃 | 関西国際空港冠水 | 死者・負傷者多数 | 空港・電力網損壊 | 土木学会報告 |
| 大雪警報 | 平成26年2月大雪 | 関東甲信地方 | 2014年2月14日〜15日 | 南岸低気圧 | 関東甲信全域 | 死者31人 | 高速道路封鎖 | 内閣府報告 |
| 噴火警報 | 御嶽山噴火 | 長野・岐阜県境 | 2014年9月27日 | 水蒸気噴火 | 山頂周辺 | 死者63人 | 登山道壊滅 | 長野県報告 |
第4章 発令時に私たちがやるべき事
ここまでで、過去の警報が発令した際に発生した自然災害で大きな被害が起きたことは理解して頂けたと思います。
発令時に私達がまずやることは「命を守る準備」です。

命を守る準備とは「いち早い情報収集」と「避難路と方法の確認」になります。
具体的にどんなことを行うかはこれから説明します!
1. 情報を素早く確認する
- テレビ・ラジオ・スマホの緊急速報を必ず確認
- 気象庁公式サイト・アプリで最新情報をチェック
- 市町村公式サイトを確認して避難所の開設状況を把握する
市町村の公式サイト内にある防災ページなどで避難所開設の情報などが掲載されています。市町村発信の情報は正確なので信頼して収集して問題ないと思います。
また、気象庁公式サイトや天気予報アプリなどを確認します。例えば大雨警報が出ている場合は雨雲の動きを随時確認しておくこと。その情報をもとに「仕事が終わる時間に帰れるか、会社内で待機しておくか」などの判断が出来ます。
映像や耳で情報を収集したい場合はテレビやラジオがオススメです。どちらも正確で早い情報収集が可能となっております。
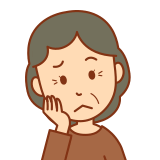
ラジオが防災商品に良いとは聞くけどどんなラジオを買ったらいいか分からない…
という人の為にオススメの防災ラジオがあります!それがこちらのラジオです!
可愛らしいデザインで多機能な防災ラジオのため、職場のデスクに置いても違和感がないラジオになっております。
2. 避難経路と避難所を事前に把握
- 自治体のハザードマップを印刷しておく
- 家族間で避難場所・連絡方法を共有
- 防災リュックに備蓄用品を詰めていつでも避難できる準備をする
避難場所を把握することで逃げるべき「安全なゴール」を把握することになります。ゴールが分からないのに走り出せないと思います。そのゴールも間違えてしまったら意味がありません。
だからこそまずはハザードマップを見て把握することが大切です。
ハザードマップは市町村の公式サイトや国土交通省が運営しているハザードマップポータルサイトでも確認できます。
ハザードマップポータルサイト
そして避難所までの距離によっては「歩いて行ける」か「走らないと間に合わない」などがあると思います。
その距離感や実際に歩いたり走ったりしてみた感触次第で防災リュックの中身を調整して下さい。
3. 発令レベル別の行動
| 警戒レベル | 住民がとるべき行動 | 対応する情報(相当)/発令基準(例) |
|---|---|---|
| レベル1 | 心構え強化:情報収集・避難準備 | 「注意報」や「警報級の可能性」など。住民が最新の気象情報に注意し、避難場所や経路を確認する段階。 |
| レベル2 | 避難準備:高齢者らは避難を準備 | 注意報や氾濫注意水位到達見込みなど、「警報級の可能性」に相当。避難の準備を具体的に進める段階。 |
| レベル3 | 要援護者避難:高齢者・障がい者は避難開始 | 大雨警報など、「警戒レベル3相当情報」に対応。高齢者等が安全を確保できるように避難開始。 |
| レベル4 | 全員避難:全ての住民は避難 | 市町村による「避難指示」レベル。自治体が発出する避難勧告などと対応。 |
| レベル5 | 緊急安全確保:命を守る行動を直ちに | 災害が発生・切迫した状態。「緊急安全確保」すなわち物理的な安全確保行動をとる段階。 |
レベル1・2では、まず「災害の可能性に備える」段階として、情報収集と避難の準備を促します。
レベル3は、避難に時間を要する高齢者等に対する避難開始の目安です。
レベル4は、危険が迫ったと判断され、すべての住民に対して速やかな避難を呼びかけます。
レベル5は、実際に災害が起きているか迫っている状態で、「安全確保行動」のみが最優先となります。
第5章 まとめ
私も東日本大震災を経験する前は「注意報?警報?なんか天気悪くなるんだな」くらいの認識でした。
ですがあれだけの大災害を経験してしまうと注意報や警報のありがたみと恐ろしさが身に染みて理解できます。
注意報が出た時点で、もう準備は始めるべき。
警報が出たら迷わず動くべき。
特別警報なんて出たら、「避難するかしないか」じゃなく「もう避難している状態」でなければ間に合わない可能性が高いです。
だからこそ今回の記事を読んで注意報や警報の種類だけではなく、どのような行動を取ることが正解なのか理解して頂けたら幸いです。
そして皆さんから周りの大切な人に周知して下さい。皆さんが共有することでさらに防災の輪が広がって多くの人が助かります。
「助けられる人」から「助ける人」を目標に是非お願いします!
そのうえで過去の災害から学ぶことは凄く大事です。なぜなら「だいたい同じ天候や災害で同じような被害が起きる」からです。
液状化のリスクがある場所はもともとの地盤が脆弱なので何年経ってもそのリスクは残ります。津波だって防波堤などのハード対策が進んでいなければ昔と同じようは被害が来ることは分かり切っているはずです。
ただ、実際に被害があった自然災害だけ学べばいいという訳ではありません。
例えば東北の東日本大震災ですが、私の住んでいた鵜住居町は過去に起きた三陸地震津波やチリ地震津波でも津波は来ても東日本大震災レベルではありませんでした。
そして昔の津波の被害を想定した防波堤などのハード対策を進めてきたからこそ私の祖父母の代からは「大きな地震が来ても津波が町を飲み込むことは無い」と教わってきました。
この教えに疑問を持って防災活動をしてきたのが私達、釜石東中学校でした。
過去の災害は一つの基準であって、それと同じとは限らない。それ以上かもしれない。
この記事を読んで下さった方々には念頭に置いて欲しいことがあります。
「行政に頼らず、自分の命は自分で守る」
という意識を持って頂きたいです。
そういった意識を持ちたいけど、何からしたらいいか分からない方は…
- 東日本大震災語り部防災士のブログを読む!
- ブログ内のお問い合わせから気軽に質問する!
- 東日本大震災の語り部を聞いてみたい!
というアクションをオススメします!
語り部を聞いてみたいという方は是非お問い合わせまで宜しくお願いします!